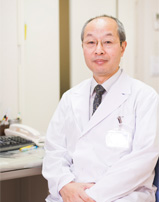- 所属:社会医療法人 大道会 森之宮病院
- 役職:心臓血管センター 心臓血管外科部長
- <経歴>
-
昭和58年愛媛大学医学部卒業。
大阪大学附属病院第一外科、大阪府立病院、桜橋渡辺病院心臓血管外科から、埼玉医科大学心臓血管外科助教授(血管部門チーフ)を経て平成18年4月から森之宮病院心臓血管外科部長。
日本胸部外科学会認定 心臓血管外科専門医・指導医
日本血管外科学会認定 心臓血管外科専門医・指導医
日本心臓血管外科学会認定 心臓血管外科専門医・指導医
日本外科学会認定医
日本胸部外科学会認定医・指導医
日本血管内治療学会評議員
日本人工臓器学会評議員
胸部ステントグラフト指導医
腹部ステントグラフト指導医
難病指定医
―― 学生時代はどのような生活を送っていらっしゃいましたか。
加藤 家庭が貧乏だったわけではないのですが、仕送りが少なく、アルバイトをすることが多かったです。卒業する段階でどの道を選ぶのかを悩んだときにまず内科はないなと思っていました。外科は身体を動かして、手を動かして仕事をすれば一人前になれるのではないかと、学生なりの単純なイメージで捉えていたこともあり、外科を選びました。
―― 卒業後は大阪に戻られたのですね。

加藤 私が卒業したのは愛媛大学なのですが、まだ医学部ができて間もない時期で、私は5期生でした。それで愛媛県内で研修しようと思っても、愛媛大学はまだ県内の基幹病院を関連施設として取れていなかったのです。今とは全く違う研修制度で、大学医局から外の関連病院に割り振られる形でしたから、基幹病院が大学に紐付けされていないと研修に行けません。それで愛媛では一人前になるのに時間がかかってしまうと考え、生まれ育った大阪に戻ることにしました。
―― 大阪大学の第一外科に入局されてからの研修医生活はいかがでしたか。
加藤 大阪大学の第一外科の医局に入り、大阪大学の初期研修を受けることになりました。当時の第一外科の中には心臓血管外科、呼吸器外科、一般消化器外科、小児外科という4つの大きな部門があり、希望を出せば、どの部門にも行かせてもらえる仕組みになっていました。最初の2年間は外科研修として、一般消化器外科から研修を始めました。一般消化器外科の主たる対象疾患はがんでした。担当医となって手術をするのですが、それ以前に虫垂炎、ヘルニア、痔、胆石症の手術などの経験は積んできていても、いざ次ががんということになると、外科手術の中でも一番のウェイトを占めている領域ですし、非常に重い責任を感じました。まだ外科医になって2、3年という段階で人の運命を決めるような手術をするのかということに大きなジレンマがありましたね。私が手術をすることで再発するのではないか、先輩やベテランの先生が手術をすれば技術の差が出て、私より良い成績になるのではないかと思い悩んだりもしました。
―― 悩んだこともおありだったのですね。
加藤 外科医の人生はそんなに長くなく、目がしっかり見えて、集中力が発揮できる55歳までがせいぜいだと思います。外科医の人生を30年だとすると、最初の15年は一生懸命に勉強して技術を高めて一人前の外科医になり、残りの15年は標準以上の治療だけにできるだけ絞って、最初の15年で患者さんに損をさせた部分を弁済しないといけないのではないかと当時は考えていましたね。
―― 心臓血管外科を選んだ理由をお聞かせください。

加藤 第一外科の手術の中で、一般消化器外科は乳腺から甲状腺までありましたのでバリエーションが多かったのですが、がんが主な対象なので、やはり再発するのです。それも2年、3年、5年というレベルで再発してくるので、患者さんはまた入院となります。その頃の化学療法はそれほど効きませんでしたし、緩和医療も今ほど充実していなかったので、一般消化器外科に進むのには迷いがありました。一方で、当時の大阪大学は心臓血管外科の中でも小児心臓外科が主流でした。チアノーゼ性心疾患の子どもさんはチアノーゼがあるので、紫色の唇や爪をしているのですが、心臓外科手術を受けることによって、それがピンク色へと劇的に変わります。集中治療室に戻った時点でそういう劇的な変化があり、その後すくすくと良くなっていく姿を目の当たりにして、これだと思いました。こんなふうに劇的に変わった子どもがその後の人生を過ごしていけるのは外科医冥利に尽きると考えたんです。それで、小児心臓外科だと医局に伝えました。
―― 最初は小児心臓外科を志望されたのですね。
加藤 ところが、そこが医局の難しいところなのです。当時の第一外科のメインストリームは小児心臓外科だったので、同期の中でも希望者が多く、皆が小児心臓外科に進めるわけではありません。一般消化器外科での研修後、次の専門外科に配属されたのは桜橋渡辺病院でした。ここは成人の心臓血管外科の施設で、子どもは一切やっていないので、子どもの手術には携われません。しかし、実際に桜橋渡辺病院に行ってみると、苦しむ患者さんが大勢いらっしゃいましたし、色々な新しい医療を見ることができました。
―― カテーテルとの出会いはいつでしたか。
加藤 その桜橋渡辺病院に行ったのが私にとっては転機でした。その当時、循環器内科でちょうど始めていたのが急性心筋梗塞に対してのカテーテルインターベーションの治療だったのです。それ以前は急性心筋梗塞の患者さんはとりあえず集中治療室に入れて、保存治療が中心でした。とりあえず寝かせとけ、あまり動かすな、不整脈が出たら抗不整脈薬を使って不整脈を抑えろと、非常に保守的な治療が行われていました。しかし、私が桜橋渡辺病院に移った頃、そこでは急性心筋梗塞の患者さんが救急車で運ばれてくると、そのままカテ室に入れ、詰まっている場所にワイヤーを通してバルーンで膨らませる、今ではほぼ当たり前の治療になっているPCIを既に始めていたのです。毎日のように運び込まれる患者さんに対し、循環器内科医がPCIを行うのですが、当時のPCIは外科医のバックアップが必須でした。私は一応、心臓血管外科医ということで、毎晩のようにカテ室で循環器内科医によるPCIを眺めていました。
―― PCIにどのような印象を受けましたか。

加藤 循環器内科医がバタバタと動き、詰まった血管や冠動脈がパカッと開いて、開いた途端にVTになります。VTになるとDCをかけ、また心臓が戻ると、上がっていた心電図上のSTが少しずつ下がっていきます。つまり再疎通されたので、冠動脈に血が流れるようになり、心電図上の変化に表れるわけです。この様子を見て、これは必ず教科書に載るような医療になると実感しました。当時の教科書では急性心筋梗塞の患者さんの第一選択は保存治療でしたが、患者さんを病院到着30分以内にカテ室に入れ、詰まった冠動脈を再疎通させるという時代が来たのを目の当たりにできたわけです。私も医師をしている間に教科書を塗り替えるような仕事をしたい、これまではこういう医療だったけれど、これからはこういうことをするのだということを医師人生の中でできたらという思いが芽生えました。これがその後に大動脈領域で新しい治療を考えるようになったきっかけでもあります。
―― その後、大学に戻られて、大阪府立病院に配属されたのですね。

加藤 桜橋渡辺病院では1年半、成人の心臓外科の研修を受けて、大学に戻りました。大学では専門領域に戻りますので、心臓外科のチームに入るわけです。もちろん一人一人に研究テーマが与えられます。ちょうど博士号を取る時期にあたっており、「加藤くんは博士号はいりますか」と聞かれたので、「そんなものはいらん」と思い、「博士号は取りません」と宣言しました。すると、外の病院に行きなさいということになり、大阪府立病院に赴任したのです。大阪府立病院の心臓外科部長は大西健二先生で、第一外科の心臓チームの中で最も手術がうまく、名人技が冴えていると言われている方でした。私は大西先生が大阪府立病院にいらっしゃると知っていたので、大阪府立病院に行ってくれと言われたときは「大西先生の技術を学ぶことで、一流の心臓外科医になれる。望んだことだ」と思いました。大西先生はかなり好みが激しく、大動脈瘤や大動脈解離に関しては得意分野で、ほかの先生方と差別化できる技術をお持ちでした。それで、私も自ずと大動脈瘤や大動脈解離に触れることが多くなりました。
―― B型解離の問題に、どのように気づかれたのですか。
加藤 大阪府立病院に赴任するときに、心臓外科のチーフの先生から「大西先生は手術はうまいけど、自分がやった手術のデータをきちんとまとめていないので、どれだけ成績がいいのか、なぜ成績がいいのかを検証できない。大阪府立病院に行ったら、大西先生の手術の成績をきちんとまとめてほしい」と言われたのです。大西先生の手術の成績は確かに外部に自慢できるものでしたが、学会などにあまり出ない先生なので、データがきちんとまとまっていませんでした。そこで私が臨床研究という形で、それまで大阪府立病院で行われた手術成績をまとめていきました。その中でB型解離の問題に気づいたのです。
―― そのプロセスをお聞かせください。

加藤 大動脈解離にはA型とB型があります。A型は上行大動脈に解離があるので、緊急手術を行います。しかし、B型解離はすぐに破裂しないことが多いので、降圧安静治療が行われてきました。治療後は一旦、外来で経過観察をします。しかし、5年ほど経ってくると、解離した偽腔や大動脈が徐々に膨らんでくることがあるので、膨らんできた時点で手術をします。当時の大阪府立病院ではA型解離は手術死亡率が5%ぐらいでした。当時はメジャーな施設で10%程度、一般的な施設では20%近くありましたので、5%というのは驚異的な良さでした。ところが、B型解離の手術成績を見てみると、死亡率が20%近くあるのです。このデータを大西先生に見せたところ、「そんなに成績が悪いわけがないだろう」と怒り出しましたが、一人一人の患者さんをまとめたデータを見せたら、納得せざるをえませんでした。それで、その原因を手術のタイミングで比べてみました。
―― どのようなことが分かりましたか。

加藤 まず、B型解離が発生したときに破裂しかかっていたり、下半身の血流が悪かったりすると手術をせざるをえないので、そういう急性期手術をした患者さんの成績は確かに良くありませんでした。ところが、亜急性期、つまり病気が発症してから3カ月以内の時期に手術をした患者さんはほとんど亡くなっていなかったのです。一旦、解離した偽腔が徐々に膨らんできて、そのうち絶対に大きくなる人たちへの手術だと成績が良く、一人も亡くなっていません。しかし、B型解離が拡大してから行った手術は死亡率が27%でした。なぜなら、B型解離が拡大してからの手術は胸腹部をまたぐことが多いので、大動脈手術の中でも最も大きな手術で、時間もかかるし、出血量も多く、色々な合併症も起こり得るからです。ただ、大西先生は手術のセンスが非常に良く、高い技術をお持ちでしたので、分割することなく、大きな手術ができたのですが、仮に私がその技術を身につけたとしても、B型解離の患者さんに手術をするとなると気が重くなりました。しかも、大西先生が手術をしても死亡率が27%あるのですから、これは根本的にこの病気(B型解離)へのアプローチが間違っているのではないかと思いました。
―― どういうことですか。
加藤 B型解離は患者さんが救急車で運ばれてきた時点で、とりあえずは降圧安静治療をして、2週間、入院させた後、一旦、外来に戻します。そして半年や1年ごとにCTを撮って、偽腔が膨らんでこないかどうかを観察し、膨らんできたら手術です。しかし、膨らんだ後に手術をすると成績が悪いので、この治療方針が悪いのではないかと思ったのです。そこで、大西先生と相談し、B型解離もA型解離と同じく、全て緊急手術で対応しようとしたのですが、実はスタンフォード大学でB型解離を急性期に手術した論文があって、その死亡率が16%と高かったことが判明しました。それを大西先生に告げて、思いとどまってもらったのです。ただ、やはり急性期、あるいは亜急性期の段階で何とか膨らまないように治療したり、処置をすることは必要だと感じ、色々と思い巡らせた結果、B型解離のエントリーをカテーテルで塞ごうと思いつきました。
―― ステントグラフトの作成までのお話を聞かせてください。

加藤 最初はパルマッツ・シャッツのステントをより大きく作り、そこにコンドームを巻いて人工血管という形に仕上げようと考えました。コンドームは当時、生理学の実験などでよく使われていたのです。このコンドーム付きステントをバルーンを載せ、エントリーの部分に持っていき、そこでバルーンをパカッと広げれば、パルマッツステントがコンドームごと広がって、エントリーを塞ぐことができるのではないかと思いつきました。この思いつきは私が考え続けていたからというものではなく、実は誰にでも思いつけることです。それを先輩の先生に見せると、「これはなかなか面白い」という意見をいただきました。教授からの反対意見もありましたが、結果的には大阪府立病院の中で色々な研究が始まったわけです。まずはエントリーを閉じるために使う人工血管を作りました。これは今ではステントグラフトと呼ばれています。
―― 実験をどのように始められたのですか。
加藤 まず、人工血管を作るために、専門家に弟子入りしました。当時、人工血管の研究をしていた国立循環器病研究センター・生体工学部という部門があり、そこの部長の松田武久先生のところに弟子入りしたのです。人工血管はあくまでヒトの身体の中に入れても構わない素材でないといけないので、最初に私が臨床応用したポリウレタンの人工血管を形成し、この内側にステント(Z-stent)を取り付けることで、ステントグラフトができました。その自作のステントグラフトを次に動物に移植していくわけです。まず実験動物(犬)の下行大動脈にステントグラフトを埋めてみると、きちんと入ったので、次に実験動物に大動脈解離を作ることになりました。しかし、2週間から3週間経過した大動脈解離犬を作る技術を習得するのに3カ月から4カ月かかりました。
―― その後の実験の推移をお聞かせください。

加藤 大動脈解離犬を作って2週間おいてから、ステントグラフトでエントリーを閉じるための実験が始まりました。当時、12フレンチのカテーテルを使ったのですが、これは犬にとってはぎりぎりのサイズで、12フレンチのカテーテルの中から自作のステントグラフトを押し出してエントリーを塞ぐという実験を繰り返しました。もちろんエントリーを閉じることはできましたので、それから犬を1カ月、3カ月、6カ月、1年という形で慢性期まで生かせて、人工血管の状態などを組織学的に観察するスケジュールを組み、実験を繰り返しました。その犬の実験でエントリーが閉じ、偽腔がなくなるという、感激するほどの劇的な変化があったのです。実験を3年ほど繰り返し、ようやく論文を書き、これを臨床応用すべきだと大西先生に伝えると、「やろうか、じゃあ、やってみろ」と言ってくれたんですね。大動脈解離にステントグラフトを入れるのは世界中でも一切、行われていませんでしたので、ある意味、本当に世界初でした。
―― 患者さんにどのように伝えられたのですか。
加藤 世界初の治療を患者さんが受けるわけですから、1回の承諾ではもちろん駄目だと考えました。それで時期を変えて3回のインフォームドコンセントを取ることにしました。また、それを実現するために、院内の倫理委員会を通す必要があり、当時の園田孝夫院長に話をしました。しかし、私には悪い予感しかありませんでした。園田先生は大阪大学泌尿器科の教授だった方で、腎移植の世界ではパイオニアです。大阪大学で腎移植を再開したときに倫理の壁が高かったはずですから、大学の倫理委員会で苦労された先生にこんな案件を持っていっても、「よっしゃ、やれ」とは言われない気がしたのです。しかし、園田先生にB型解離の患者さんにステントグラフトを適用したいと伝えると、5分ほど気まずい沈黙がありましたが、「やってよし」と言ってくれました。私は単純に喜んで、大西先生に伝え、X-デイを決めて、患者さんにステントグラフトを植え込みました。
―― ステントグラフトは最初から成功したのですか。

加藤 いえ、最初の3例はことごとく失敗し、がっかりする結果でした。動物実験の段階では全てパーフェクトに閉じられたエントリーを閉じることができなかったのです。動物実験では最もステントグラフトを入れやすい場所にエントリーを作り、それを目がけてステントグラフトを入れるので綺麗に閉じられたのですが、実際のヒトのエントリーの場所はそんなに都合のいい場所にありません。左鎖骨下動脈のすぐ近傍にあることが多いです。そこには大動脈のカーブがあり、しかもカーブの変曲点にエントリーがあることが多いんです。難しい場所のエントリーはカテーテルではスムーズにいかず、立て続けに失敗しました。患者さんのエントリーを綺麗に閉じられなかったのが2人で、その中の1人はステントグラフトが大動脈の中でポキッと折れ曲がってしまったので、大トラブルでした。大西先生がすぐに入ってこられ、いわゆるリカバリー手術をしてくださいました。ステントグラフトを取り出して、普通に人工血管置換という形になったのですが、幸い患者さんは合併症もなく、自宅に帰られました。結果オーライでしたが、3人が立て続けに良くなかったので、大西先生からは「もう止めてまえ」と言われました。止めるべきだったのかもしれないですが、私としてはこのステントグラフトのプロジェクトに対し、3年間、精神的にも肉体的にも追いこんで、想像もつかないレベルで努力をしてきたのです。3人の事例は悔しかったものの、やり続けるという決定を自分の中で下し、その後もできるだけエントリーを閉じられそうな患者さんを見つけて、やり続けることにしました。ある程度、落ち着いてくるのに15例ほど必要でしたが、この患者はエントリーを閉じれる、閉じれないということが徐々に分かってきて、成功するようになっていきました。成績は落ち着いてきましたが、最初の3例がうまくいかなかったことに関しては自分なりに解決をしておかないと納得がいきませんでした。
―― どのように解決されたのですか。
加藤 大動脈がカーブしている場所にステントグラフトを入るとエントリーを閉じられないことが特に多かったのはカーブの小弯側に血液が入り込むスペースができてしまうからです。これはバードビーク(鳥のクチバシ)と呼ばれているスペースです。このバードビークができ、エントリーを閉じれませんと、慢性期にはやはり膨らんでくるので、なんとかこのステントグラフトでエントリーを閉じ、慢性期に膨らまないようにできないものかと悩みました。そうするとふと、良いアイディアが浮かぶものです。つくづく考えた結果、そもそも私は外科医なのだから、漏れやすい場所は縫えばいいと思いました。漏れるのは中枢側、心臓側です。その心臓側のステントグラフトの小弯側が浮くので、血管の漏れになます。そこで中枢側を縫って、末梢側はステントで手術すれば、エントリーを確実に閉じることができると思いつきました。そのタイミングで大西先生が異動になり、リカバリーしてもらえないリスクを含め、慎重に、慎重に、万全の体制で、最初の手術に臨みました。実はこの手術が心臓血管外科界で一般的に行われているオープンステントグラフトであり、海外ではフローズンエレファントトゥルンクと呼ばれているものです。この手術は私が考えたオリジナルの手術です。この手術方法は私の意図とは全く異なり、世界中に広がり、今では1年間に1万人以上の患者さんが受ける手術になりました。次に、私はB型解離に対するカテーテル治療やステントグラフトを使った治療の標準化を目指そうと思いました。それで1988年に臨床実験データをまとめて、論文化しました。1998年に「大動脈解離をステントグラフトを使って治療した」という世界初の論文が、Circulationにパブリッシュされました。
―― B型解離に対するステントグラフトを使った治療を標準化するまでのプロセスについて、お聞かせください。
加藤 標準化させるためには日本ではまず保険治療ですが、そんなにひとっ飛びに保険治療になるのは難しいです。そこで最初に考えたのは高度先進医療として申請し、それが認められたら、世間一般にじわじわと広まっていくので、限られた施設の中でしようということでした。ところが、ステントグラフト自体も新しいですし、そういう新規の医療材料を使って、新しいコンセプトや考え方でとなると、行政の壁は高いんです。高度先進医療の委員会からは「新規のデバイスを使って、新規の治療方法というのはいまだかつて1件もない」と、ほぼ門前払いを食らいました。その次に考えたのはランダマイズ試験です。ランダマイズ試験は今では当たり前ですが、当時はそれなりにハードルが高く、計画をしたものの、実行には至りませんでした。私が考えた計画はカテーテル治療をした群と降圧治療をした群に分けて、大動脈がどのように膨らむのか、膨らまないのかを見極めるといったものでしたが、患者さんにサイコロを振らせて、「あなたは降圧治療ですよ」とは言えません。全ての患者さんにステントグラフトを入れて、「これでB型解離が治りますよ。将来、膨らむことはありませんよ」と言いたいですからね。
―― 結局、ランダマイズ試験は行われなかったのですか。
加藤 いえ。ドイツのニナバー先生が2006年にプランを立て、ランダマイズ試験を始めて2年の結果が2009年、5年の結果が2013年に出ました。2年の結果は良くなかったのですが、5年の結果では生命予後に関しても、大動脈解離に関しても、両方とも降圧治療とは明らかな差が出て、ステントグラフト治療が慢性期の拡大を防ぐことが分かりました。私自身にこれができなかったのが心残りですが、ニナバー先生がランダマイズ試験を行ってくれたので、発症後1年以内にステントグラフト治療を行えば、生命予後も大動脈解離も良くなるという証拠を得ることができました。それがエビデンスとなり、それに伴ってガイドラインが書き換えられ、行政も動くという筋道ができあがりましたので、私にとっては非常に嬉しい結末を迎えました。
―― 一度、医師を辞められたときのお話をお聞かせください。

加藤 阪大の第一外科の医局の中でB型解離の患者さんを大阪府立病院にまとめてくれないかという提案をしたのです。患者さんを積極的に集めて経験値を上げたかったのとランダマイズ試験を検討していたからです。ところが、当時の教授はそういう仕事は大学の仕事だと思っていたようで、少し怒り始めて保留になりました。ちょうど同じ時期に国立循環器病研究センターの外科部長だった高本眞一教授から移籍のオファーがあり、私としては嬉しく、本当に行きたいと思いました。国立循環器病研究センターぐらいの病院でしたらB型解離の患者さんも多いですし、ランダマイズ試験もできると考えました。ところが、それを医局に伝えると、「行くな。お前のレベルで断れ」とストップがかかりました。その時点では医局と決別するつもりがなかったので、行かないことにしたのですが、医局とは一体何だと思い始めました。私がしたいことに対して、ほかの施設に迷惑をかけない形で患者さんを集約させるプランを立てたり、あるいは私のステップアップは医局に迷惑をかけないはずなのに、実現させてもらえないというのは何だということです。医局が私にしてくれたことは外科医として一人前になるために絶対に必要なことです。桜橋渡辺病院でカテーテル治療の醍醐味を知りました。そして大阪府立病院で大西先生の下で心臓血管手術の勉強ができました。これらのすばらしい施設に出向できたのは医局のおかげですし、この出向がなければ今の私はもちろんいません。医局への恩返しをしないといけないと考えていましたが、自分のしたいことが次々に出てきて、さらにステップアップできるという時期にスムーズにいかなくなると、思い悩んでしまいました。医局を離れて、どこかに行く選択肢もありましたが、一旦リセットしようということで、40歳のときに医師を辞めたのです。
―― 医師を辞められて主夫になられたとのことですが、そのあと医師へ復帰されたお話もお聞かせください。
加藤 医師を辞めたときは外科医としての仕事は一通りやり切ったという達成感があり、医師にはもう未練はない、経済人になって金融の世界に入ろうと思いました。妻が歯科医師でしたので、お金のことは心配せず、主夫をしながら経済学の勉強を始めたのです。主夫はそこまで仕事が多いわけではありません。炊事、洗濯、掃除は2時間から2時間半あればできるのです。しかし、医師の仕事と全く違うのはモチベーションが湧かないことでした。残念ながら炊事、洗濯、掃除に対する評価は誰からも受けられません。毎日、家事をし続けるのは苦痛で、やる気にならないのです。医師の仕事を振り返ってみると、結果の良し悪しに関わらず、評価されます。患者さんが亡くなられた場合でも一生懸命やった結果なので、ご家族から「ありがとうございます」と感謝されます。社交辞令かもしれませんが、そんな仕事は少なくともほかにはないと思います。医師の仕事は医師としての仕事を単純にするだけで高い評価をしていただけ、その評価がモチベーションになるので、こんなにいい仕事はないと思い直しました。経済学の勉強も行き詰まっていましたので、やはり医師に戻ろうと考え、埼玉医科大学にお世話になることにしました。
―― 内科と外科の今後の医療の方向性について、先生の見解をお聞かせください。
加藤 時代にはそぐわないかもしれませんが、私の頭の中では内科は基本的に診断学です。病気の診断をつける、あるいは病気の原因になったものを探すのが内科医の仕事です。一方、外科は基本的に治療学です。病気が発症してから治療を行うのが外科医というイメージです。しかし、循環器内科医がPCIをしたり、不整脈や心不全の治療を主導したりしていますし、今では心臓弁膜症に関しても内科医が主導したりなど、内科医が治療学に入り込んできています。消化器分野でも外科はお腹などを切る外科手術をしてきましたが、内視鏡手術が出てきて、腹腔鏡下手術が一般的になりました。しかも内視鏡手術には消化器内科医も携わっています。診断学が中心だった内科医が外科領域に入り込んできているのです。したがって、そこを内科・外科で分けて考える必要はないですし、診療科を選ぶにあたっては外科でも内科でも自分がしたいことは診断学中心か、治療学中心かで選べばいいと思います。外科医のあり方も変わっていくでしょう。手術治療やカテーテル治療に加え、薬の治療もあります。外科医も普通に薬を処方できますから、大動脈瘤や大動脈解離が薬で治せるのなら外科医が薬で治療してもいいはずです。外科医は手術も薬での治療も勉強できますから、バリエーションがとても広いです。是非、取り組んでいただきたいです。
―― ダヴィンチやAIについて、先生のご意見をお聞かせください。
加藤 ダヴィンチを見ていると、人の手では入れないような場所にアームが入り込み、必要な場所を切開できたりするのですごいですね。これまで視野が悪かったり、とても狭い場所で針を回したり、メスをいれるのが難しい部分に優秀な機械が入って名人技を代行してくれるのですから、機械によって医療が標準化します。今後、ダヴィンチの名人技は全世界の外科医療に普及していかなくてはいけません。私がよく学会でお話しするのですが、「名人が死んでしまったら、誰もそれを引き継ぐことができない。名人が教えても名人の教えた弟子が名人をリプレースすることは決してない。そこには大きな段差ができてしまう」ということです。しかし、名人技がダヴィンチに引き継がれたとしたら、皆ができることになるので、患者さんにとってはそちらの方が絶対に利益になります。また、AIは診断学に近々入ってくるでしょう。これもすごいことです。例えば、画像診断に関しては人の目よりAIの診断の方がはるかに正しいということになるのです。私たちが見えなかった部分、見逃していた部分をAIが見つけてくれるとなると、これも医療の標準化に繋がります。いわゆるハイテクノロジー分野はこれからの医療の中でますます重要になっていくはずです。