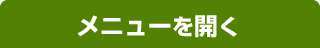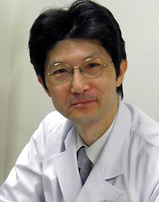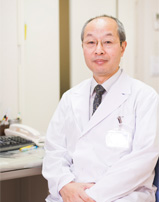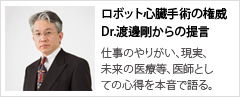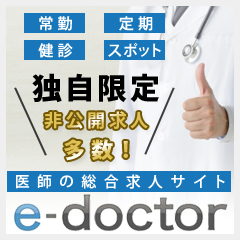能登半島地震の被災地にはいらっしゃいましたか。

行きましたよ。東日本大震災のときに石巻圏合同救護チームで被災地をエリア、ラインに分けたお話は以前もしましたが、石巻市の北側にある雄勝地区もエリア化しました。
雄勝地区は今は石巻市の一部ですが、合併前は牡鹿郡雄勝町といって、雄勝硯で有名なところです。その雄勝地区は壊滅状態になりましたが、そこに石川県チームが2ラインをずっと出してくれていたんです。
その後、雄勝の人たちは石川県の人たちとすっかり仲良くなり、復興後に金沢に遊びに行ったりという関係になりました。石川県の方々にはとてもお世話になったのですが、この地震で立場が逆になり、石川県が被災地になったので、これは恩返しをしなくてはいけないなと思いました。
どのように支援を始められたのですか。

公立能登総合病院の圓角文英先生は地域のDMATの中心を担っている方なのですが、私が事務局長を務めている災害医療ACT研究所で災害医療コーディネート研修の講師をしてくださったりしたご縁があるので、その圓角先生に電話をしてみると、本当に大変な状況で、避難所の様子は当時の石巻と同じような感じだということでした。
以前の連載でもお話ししましたように、私には熊本地震のときの黒歴史があり、二度と現場には行かないと思っていたのですが、これは恩返しをすべきだ、DMATとは別に宮城県から1ラインでも救護班を出すべきだと考えました。それでDMAT事務局の近藤久禎先生に電話すると、東日本大震災では知事会の枠組みで、県が県に支援を出すというシステムになっていたのですが、今回はそのシステムはなく、DMAT以外の救護班はJMATに依頼するシステムになっていると分かりました。
それで「JMATとして来るといいんじゃないか」というお話をいただいたので、私は宮城県医師会の常任理事ですし、会長は佐藤和宏先生といって、テニス部の先輩なので、佐藤先生に電話をしました。すると「あのときは日本医師会にも大変お世話になったので、是非支援してくれ」と快諾してくださいました。
それでラインを組まれたのですね。

石巻圏合同救護チームで一緒にエリア化、ライン化したメンバーの山内聡医師に相談をしました。何かあったら、いつも彼に相談するんです。
山内医師は東日本大震災当時は東北大学病院の救急部にいましたが、現在は仙台市立病院の救命救急センター長を務めています。DMATには救急科の先生方が多いので、彼は宮城県のDMATの部会長ですし、各病院に募集をかけてくれることになりました。
そのときに「募集は私がしますが、条件があります」と言われたんです。「先生は第1隊で行ってもらわないと困ります」という条件でしたので、私はJMAT宮城の第1隊のチームリーダーとして、1月13日に現地に入りました。
現地ではどのような活動をされたのですか。

DMATが市立輪島病院で活動してもらえるように事前に調整したりしながら、14日からの4日間は市立輪島病院の発熱外来を担当しました。
1日30人を超える被災者の方を診ましたが、簡易検査キットでの判断でも4割の方が新型コロナウイルスかインフルエンザに感染しており、感染症が流行していると言える状況でした。
一方で、災害医療ACT研究所で取り組んでいる自動ラップ式トイレの「ラップポン」の配布事業を行い、トータルで599台のラップポンを配りました。このラップポンは用を足すと排泄物が1回ずつ特殊な防護フィルムで包装され、凝固剤とともに密封できるので、水が必要ありません。仮設トイレのように段差もなく、屋内に設置でき、臭いも全くなく、水洗トイレと同じような感覚で使えるので、被災者の方々にはとても喜んでいただけました。
熊本地震と比較して、いかがでしたか。

熊本地震ではコンビニエンスストアも営業していましたし、断水も少なかったのに対し、能登は石巻でリアルに見た光景と全く同じでした。
断水でトイレもなかなか流れず、埃っぽいんです。そこに輪島市をはじめ、色々な自治体の方々が入って避難所をマネジメントしたり、ボランティアベースで入った人たちが頑張っているというのも同じでした。
ただ石巻は避難所は断水もあって酷かったのですが、道路のアクセスは良かったんです。津波による瓦礫を除けば通れる道になるので、自衛隊の方々ががーっと瓦礫を除き、道を作ってくれました。
しかし能登は道路事情が悪く、これは地元の方々は大変だろうと思いました。その中でも被災地の方々が不満や怒りを訴えることなく、非常に我慢強く耐えながら淡々と仕事や生活をされている姿が印象に残りました。
被災地では災害医療のお仲間にも会えましたか。

熊本地震での苦い経験があったので、指揮を取ることなどはせず、一救護班員に徹していたのですが、本部では「待ってました」と言われたり、日赤の救護班の知り合いから声をかけられたりしました。
私はそののち2回ほど個人レベルで被災地に行き、レンタカーを借りて、どこの避難所にラップポンが必要なのかを調べたり、ラップポンを配ったりしました。