東北大学医学部は首都圏の高校生にも人気がありますね。

確かに首都圏の高校生から人気のようですが、それは首都圏からアクセスしやすいという地の利も大きいでしょう。私がアドミッション・ポリシーを決めているわけではないので、偉そうなことは言えないのですが、東北大学では「門戸開放」と「研究第一」という理念を掲げていますし、医学部としてもAOII期やAOIII期では探究心や好奇心が強い学生を求めているのかなと思います。
先生から見て、東北大学の学生さんはどんな方々ですか。
私は東北大学の学生は好きですね。どこが好きかと言うと、物怖じしないところや探究心が非常に強いところです。以前、医学部の学生に卒業後の希望する進路についてのアンケートを取ったのですが、ある程度の大きな都市の大きな病院で専門医を取得したいという志向が強く、開業志望の学生はあまりいませんでしたし、勤務医として探究心を発揮していきたいのかなと思います。
こういう高校生にこそ、医学部を目指してほしいという高校生像をお聞かせください。

東北大学の理念が「研究第一主義」ですし、学生に向けては「フィジシャン・サイエンティストを目指すように」と提案しています。診療だけの医師だと単なる技術者になってしまいますし、手術の方法やスキルだけ学んだ医師では患者さんの問題を解決するには限界があります。患者さん一人一人が色々な病気をお持ちですし、患者さんが抱えている問題は基本問題ではなく、応用問題です。しかも最近は高齢化が進み、患者さんの背景が複雑化しています。その中でどれを優先して治療すべきなのかを決めるにあたっては総合的、俯瞰的、論理的、科学的に思考する能力が必要です。例えば外科で言えば、がんが主要な疾患です。この患者さんにはがんの治療が必要だけれど、心臓や肺も悪いからどうしようかというときに「手術するならこのぐらいの手術にしようか」「手術は難しいから化学療法にしようか」といった総合的な判断が必要です。標準治療でありながら、患者さん一人一人に合わせて、微妙にカスタマイズするオーダーメイドの治療を提供していますので、それには科学的な思考能力が必要であり、それがあるかないかでは臨床医としての力量は大きく異なると私たちは信じています。
科学的な思考能力について、もう少し詳しくお聞かせください。
総合診療科的に言うと、低蛋白血症の患者さんがいたとします。低蛋白血症になる理由としては、身体の中でタンパク質を作れないか、身体からタンパク質が逃げていくかのどちらかです。もし身体の中でタンパク質を作れないのであれば、その原因は肝臓が悪いからではないかと調べていきます。そこをクリアして、タンパク質を作る能力があるのだとしたら、身体からタンパク質が逃げていることになります。もし逃げているのだとしたら、どこから逃げるかと言うと尿か、便です。そのどちらかを調べるには尿と便の両方のチェックが必要であり、便から逃げているのであれば、蛋白漏出性胃腸症だと考えてほしいわけです。「低蛋白血症ですので、アルブミンの点滴しますね」と言うだけの医師にはなってほしくないし、思考停止して「分かりません」で終わってしまう医師にもなってほしくありません。こういう思考を巡らせるトレーニングの一環として、研究があります。
やはり研究は大切なのですね。
研究はやってみると新しいことが分かったりして面白いですし、医学の進歩にも繋がり、遣り甲斐もあります。ただ、「研究第一」を掲げる大学の人間がこういうことを言うと怒られるかもしれませんが、医学部に入学する学生はほとんどが臨床医をしたくて入学しているので、卒業後もほとんどが臨床に進みます。そこで、東北大学では良い臨床医になるためには研究に向かうリサーチマインドや探究心、科学的な思考回路を持つことが重要だという提案をしています。
高校生が探究心を育むためにはどういった訓練が必要でしょうか。

個人的な意見ですが、本を読むこと、読書量を増やすことですね。小説でいいので、本を読み、日本語力を鍛えてほしいです。私は急に教授になれと言われ、市中病院から大学病院に戻ってきました。そして教授の先生方と一緒に仕事をしたり、触れ合う機会が増えました。大学にいると、先生方がお書きになった申請書や報告書、外部資金や研究資金を獲得するための研究計画書などの文書を見たり、参考にさせてもらうことがありますし、先生方とのメールのやり取りも多いです。先生方皆さん、日本語が理路整然としていて、超お上手なんです。どなたの文章も綺麗で、頭にすっと落ちます。意味の分からない文章を書く人は一人もいません。これが大学に戻ってきて、本当に驚いたことでした。これはどうしてだろうと考えると、やはり日本語をきちんと書くには論理的な思考能力が要求されるのだと気づきました。日本語は主語や動詞の使い方が難しいですし、主語を省略できることもあり、ある意味で英語よりも難しい言語です。相手の頭の中に入るように、相手に伝わるように文章を書くのは難しいものなので、私は小説家はもちろん、新聞記者などのマスメディアの方々を尊敬しています。私としてはその力をどうやって培っていくかというと、読書かなと思います。ただ本を読まない人が全員、文章が下手かと言うと、そういうわけではありませんが、日本語を上達させるには読書をして、日本語に触れる機会を増やすことが大切です。読書をして、語彙力を増やすというよりも、人に納得してもらうためのロジックを身につけていきましょう。


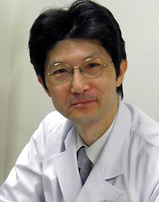 精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
 がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
 医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
 私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
 次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
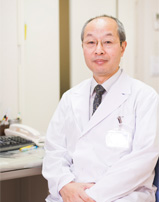 若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長
若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長