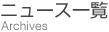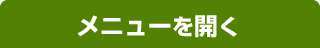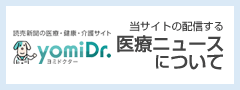-
【ベルリン=工藤彩香】ドイツの有力紙ツァイトと南ドイツ新聞は12日、ドイツの対外情報機関が2020年、新型コロナウイルスが中国・武漢のウイルス研究所から流出した可能性が高いとの極秘報告書をまとめ、独首相府に提出していたと報じた。
報道によると、独連邦情報局(BND)は、19、20年に執筆された新型コロナウイルスに関する未発表論文などを入手して分析。報告書では、武漢のウイルス研究所が、人間に感染しやすいようウイルスを改変する実験を行っていたと指摘した。ウイルスの扱いはずさんで、多くの安全規則違反があったとし、ウイルスが研究所から外部に流出した可能性が「80~95%」で非常に高いと結論付けた。
ウイルスの発生源を巡っては、研究所から流出した説と、動物を介して人間に感染したとする説とで論争が続き、23年6月公表の米政府の報告書でも原因特定には至らなかった。BNDの報告書は米中央情報局(CIA)にも共有されたといい、今後、論争に影響を与える可能性もある。
-
微小な穴が規則正しく並んだ「結晶スポンジ」と呼ばれる物質を使い、従来は難しかった大きな分子の構造解析に成功したと、東京大の藤田誠・卓越教授らのチームが発表した。次世代薬の材料を探す研究に応用が期待されるという。論文が5日、科学誌ネイチャーケミストリーに掲載された。
医薬品の材料になる物質の分子構造は、効果などに影響するため、X線を使った正確な解析が求められている。解析には分子が規則正しく並んだ「結晶」を作る必要があるが、難易度は高く、時間もかかっていた。
チームはこれまで、結晶化したスポンジ状の物質に、解析する試料を染みこませる「結晶スポンジ法」と呼ばれる手法を開発。一つ一つの穴に試料の分子を整然と並べることで、結晶化した時と同様の解析ができる。
チームは今回、この手法を改良した。従来の手法は、サイズの小さい「低分子」しか解析できなかったが、分子をとらえる穴をかご状にすることで、より大きい「中分子」の解析も可能になった。
さらに従来は難しかった水に溶けやすい試料の解析も可能になり、活用の幅が拡大。1試料あたりの解析時間も1か月から1日に短縮し、100種類超の構造を数か月で解析できたという。
中分子の化合物を使った「中分子薬」は、既存薬で治療が難しい病気にも効果のある次世代薬として研究が進む。藤田氏は「(自然界には)薬の元になる無数の宝がある。通常は検知さえ難しい物質を解析し、創薬につなげたい」と話す。
藤田氏は、分子がひとりで組み上がる「自己組織化」という現象を利用し、様々な形状の物質を作り出す研究を進めてきた。結晶スポンジ法も、この研究の応用で開発され、藤田氏は一連の成果でノーベル化学賞の有力候補にも名が挙がる。
河野正規・東京科学大教授(結晶化学)の話「解析例はまだ少ないが、今後様々な中分子に適用できれば、創薬の効率化などに貢献すると期待できる」
-
医療費が高額になった場合に患者負担を抑える「高額療養費制度」の見直しを巡り、政府が示した修正案通りに負担の上限額が引き上げられると、制度の対象となっていた患者の7割以上で自己負担が増えるとの試算を、東京大の五十嵐中・特任准教授(医療経済学)が26日、明らかにした。がんだけでなく、循環器疾患や糖尿病など幅広い病気に影響が及ぶとした。
試算は、健康保険組合と国民健康保険に加入する70歳未満の約4900万人について、2022年度の診療報酬明細書(レセプト)データから推計した。同年度に1回でも制度の対象になったのは約187万人。修正案通り見直しが進むと、少なくとも約8万4000人(4%)が制度の対象外になるなど、約136万人(73%)が現行制度より負担が増えた。疾患別にみると、大腸がんや乳がんなど固形がんが約28万人、循環器疾患が約78万人、糖尿病が約41万人だった。
政府は昨年末、制度の上限額を今夏から段階的に引き上げる見直し案を示した。これに対し患者団体が反発。今月14日、長期治療が必要な患者の負担を軽減する「多数回該当」を現行制度のまま維持する修正案を示した。
26日、東京都内で記者会見した全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長は、今回の試算について「負担増となる患者が、様々な病気でこれほどいるのは深刻だ。いったん立ち止まり、見直しを凍結、修正する必要がある」と訴えた。
-
胃カメラで採取した液体を調べることで早期の膵臓がんを高精度に発見する手法を開発したと、大阪大などのチームが26日、発表した。5年後の実用化を目指すという。論文が国際医学誌に掲載された。
胃カメラで採取した液体を調べることで早期の 膵臓すいぞう がんを高精度に発見する手法を開発したと、大阪大などのチームが26日、発表した。5年後の実用化を目指すという。論文が国際医学誌に掲載された。
-
2024年に実施された脳死下の臓器提供130件のうち、過去最多の83件が休日に集中していたことが読売新聞のデータ分析でわかった。前年に続き高止まりしており、移植施設の人員や病床が逼迫し、臓器受け入れの見送りにつながっている可能性がある。厚生労働省は、患者が登録する移植施設を複数にするなどの対策を進めており、効果が上がるか注目される。
厚労省の調査によると、院内態勢が整わないことを理由に臓器受け入れを見送ったのは23年で26施設、患者数は延べ803人に上った。理由の一つとして、臓器の摘出手術が休日に偏り、移植施設への臓器の受け入れ要請が休日に集中したことが挙げられる。
日本臓器移植ネットワークの発表資料を本紙が集計し、独自分析したところ、24年の臓器提供件数は130件で、前年(132件)に次ぎ2番目に多かった。そのうち、摘出手術が土日祝日に行われたケースは過去最多だった前年より2件多い83件(64%)に上った。
休日への集中は年々増加傾向にある。19年までの5年間の平均41%に対し、24年までの5年間は同61%に拡大した。結果として、同日に複数の摘出手術が行われた日が24年は27日(うち休日は22日)と過去2番目に多かった。
背景には、平日はがんや心臓病など通常の手術予定で埋まっており、予定外に入ってくる臓器摘出手術は休日に回されるケースが多いほか、休日の方が脳死者の家族が看取りのために集まりやすいことがある。
特に、心臓、肺、肝臓は一部の医療機関に移植手術の受け入れが集中する傾向にある。本紙の分析では東京大、京都大、東北大の上位3機関で移植手術の51%を占めた。
厚労省は、移植施設が臓器受け入れを見送っても、移植を待つ患者が別の施設で移植を受けられるように、患者が登録する施設を複数化する対策を進めている。
-
患者一人ひとりの血液からオーダーメイドのiPS細胞(人工多能性幹細胞)を全自動で作る京都大iPS細胞研究財団(理事長=山中伸弥・京都大教授)のプロジェクトが4月、大阪市北区にある最先端医療の国際拠点「中之島クロス」で始動する。年内にも大学や企業に試験的に細胞の提供を始め、将来は年間1000人分の作製を目指す。
山中教授は2019年に「my iPSプロジェクト」を提唱。「みかん箱くらいの密閉された装置の中で、iPS細胞を全自動で作れるようにする」と構想を語った。その後、国内外の企業と研究を進め、装置がみかん箱より一回り大きい点を除けば、ほぼ実現可能な段階にきたという。
中之島クロスではドイツ製の自動培養装置を4台から14台に増やし、iPS細胞を安定して作製できるラインを構築する。日本製の装置の開発も進んでおり、1人分で5000万円かかるとされた製造コストを、100万円以下に抑える目標を掲げる。
再生医療に使うiPS細胞は、健康な人の血液から作って財団が備蓄する細胞が大半を占めている。山中教授らは、これまでに日本人の4割に適合する細胞をそろえたが、さらに増やすには珍しい型の細胞を持つ人を見つける必要があり、難しいという。今回のプロジェクトで患者本人から安くiPS細胞を作れるようになれば、理想的な形で補完できる。
財団の塚原正義・研究開発センター長はプロジェクトについて「患者の治療に使われなければ意味がない、という思いで進めてきた。医療現場に届けるまでやり遂げたい」と話している。
-
全身の筋肉を動かせなくなる難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の患者の脳波などを測る電極シートを脳に貼り付け、意思を文字で表すシステムの治験を、大阪大発の新興企業「JiMED」が2025年10月にも申請することがわかった。機器を頭内に埋め込むタイプの治験は国内で初めて。28年頃の実用化を目指す。
「ブレーン・マシン・インターフェース(BMI)」などと呼ばれる技術で、埋め込み型のほか、頭の外側に取り付けるタイプがある。埋め込み型では実業家のイーロン・マスク氏が設立した米企業など2社が臨床試験を始めている。
システムは、ジーメドに所属する阪大の平田雅之特任教授(脳神経外科)らのチームが開発した。〈1〉送信機付きの薄型の電極シートを頭蓋骨と脳の表面の間に取り付け、脳波を測る〈2〉人工知能(AI)に学習させた脳波のデータを基に、患者が脳内で手を握るイメージをしたかどうかを解読装置が判別〈3〉解読装置に接続された機器の画面に文字が映し出される――仕組みだ。
機器の画面には、ひらがなが1文字ずつ切り替わりながら表示される。思っている文字が映し出された時に手を握るイメージをすると、脳波が決定ボタンの役割を果たし、その文字が入力される。その動作を繰り返し、文章にする。
治験では阪大病院など3施設で体がほぼ動かせない状態の患者11人に半年間使ってもらい、安全性と有効性を確かめる。
-
慶応大などの研究グループは13日、目の難病「網膜色素変性症」で失明した患者の視覚を再生させる遺伝子治療薬の治験を開始し、1例目の投与を終了したと発表した。成功すれば、失明した患者の視覚を回復させる新しい治療法になる可能性がある。
網膜色素変性症は、網膜で光を感知する「視細胞」が働かなくなる遺伝性の病気で、進行すると失明する恐れがある。4000~8000人に1人が発症し、確立した治療法はない。
研究グループは、光センサーの役割を持つたんぱく質の遺伝子を独自に開発。眼球に注射し、網膜の細胞で光を感知する機能を回復させる治療を考案した。早ければ1か月ほどで効果が表れ、1回の注射で効果が続くことを見込んでいる。動物実験では光への反応が回復し、病気の進行を遅らせることを確認した。
1例目の治験は6日に慶大病院(東京)で実施し、患者の失明している片方の眼球に注射した。治験は6~15例実施し、経過を約半年間観察して安全性や有効性を確かめる計画だ。グループの栗原俊英・慶大准教授(眼科学)は、「日常生活が送れる程度の視覚の回復を目指し、数年以内に実用化したい」と話す。
岩手大の冨田浩史教授(視覚神経科学)の話 「光を感じるだけでなく、物が見えるなど日常生活で有用な視覚が得られるかが課題になるだろう」
-
国立がん研究センターは13日、2012年にがんと診断された患者約39万人の10年生存率が54・0%だったと発表した。11年に診断された患者を対象とした前回調査より0・5ポイント上昇した。診断から一定年数生存している人の「サバイバー5年生存率」も初めて公表した。進行したがんでも、診断から1、2年を乗り越えれば、その後の生存率は上がる傾向がみられた。
全国のがん診療連携拠点病院などが参加する「院内がん登録」の大規模データを集計した。純粋にがんのみが死因となる場合を推定した「純生存率(ネット・サバイバル)」を算出した。部位別の10年生存率は、前立腺がんで84・0%、乳がん(女性)で82・5%、大腸がんで58・1%、胃がんで57・9%などだった。
また今回は、診断から5年後まで生存していた人を対象に、年を経るごとの5年後の生存率を示す「サバイバー5年生存率」を、がん以外の死因も含めて算出した。胃がんで最も病期が進んだ4期では、診断された年の5年生存率が5・5%だったが、診断1年後に生存していた人では、5年生存率が12・3%となった。さらに診断5年後に生存していた人の5年生存率は61・2%となるなど、多くのがんで診断から生存年数を重ねるにつれ、5年生存率が上昇する傾向がみられた。
同センター院内がん登録分析室の石井太祐研究員は「サバイバー5年生存率は、患者へ明るいメッセージになる」と話している。
-
医師が不足する地域を対象に、厚生労働省が診療所の承継や開業の支援事業を始める。高齢医師の引退や後継者不足により、2040年には全国の自治体の2割で診療所が消滅するとの試算もある中、診療所の建物や設備の整備費、人件費を補助する。都市部に医師が集中する偏在解消の観点から、24年度の補正予算に102億円を盛り込んだ。
事業費は、厚労省と都道府県が出す。都道府県が、偏在対策を重点的に進める区域を指定し、全国の医師に重点区域内の診療所の承継や新規開業を募集する。
都道府県の呼びかけに応じた医師には、建物の改修、医療機器の更新に関する費用の一部を補助する。医師や看護師の人件費やマスク、アルコール消毒液など消耗品の購入費の一部も、区域内での診療が軌道に乗るまでの一定期間、補助の対象とする。
厚労省によると22年時点で、診療所がない市区町村は77にのぼる。今後、全国の診療所の医師が75歳で引退し、承継や市区町村内での開業がないと仮定した試算では、40年には4・4倍の342になる。全市区町村の2割に相当する。診療所が1か所のみの市区町村は175から249に増える見込みだ。
民間信用調査会社の帝国データバンクのまとめでは、24年に、診療所の休廃業・解散は587件で、比較可能な00年以降、過去最多を記録した。同社は、「増加している最大の要因は、経営する医師の高齢化」と分析している。
日本医師会総合政策研究機構の19年調査では、全国の診療所の半数が「現段階で後継者候補はいない」と回答した。山形県米沢市で田中クリニックを開業する田中雄二院長(68)も、体力の衰えに不安を感じ、後継者を探しているが難航している。1日60~80人が受診、外来の合間に訪問診療も担う。
同県は、医師の充足度を示す医師偏在指標でワースト8位となっている。田中院長は「近隣の開業医も高齢で、このままでは地域住民を診る医師がいなくなる恐れがある。経済的な支援で、後継者が見つかることを期待する」と話す。
厚労省は、重点区域で働く医師の手当の増額や、都市部で働く中堅・シニアの医師に、医師が不足する地域の医療機関を紹介する事業も始める。補助事業と合わせ、都