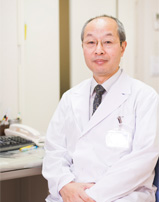小さい頃はどのようなお子さんでしたか
私が生まれ育った長野県大町市は今も市ではありますが、人口が3万人を切っているようなところです。私がいた頃はまだ35000人ぐらいで、小学校も1000人規模の大きな学校でした。私は毎日、放課後に草野球をして遊んでいましたね。
小学6年生のときに、アポロ11号の月面着陸があり、担任の先生が「授業をするより、もっと大事なことが世界で起こっている。これをずっと見てろ」とおっしゃって、体育館で月面着陸の瞬間を皆で見守りました。その先生は非常に良い先生で、「こんな田舎に住んでいても、常に志を持っていれば、何でも成し遂げられる。志の大小は関係なく、志を持って生きていくことが大事なのだ」とおっしゃっていたのが今でも心に残っています。
医師を目指したのはいつですか
意識しはじめたのは中学生の頃です。私が中学、高校の頃の長野県はリベラルな雰囲気があった一方で、自由に高校を選べる時代ではありませんでした。私は、いわゆる進学校がある、松本市の高校に行きたかったのですが、大町市や白馬村周辺の数校しか選べなかったのです。
白馬といえばスキーですが、私はスキーが苦手だったので、少し迷いましたが、大町高校に進学しました(笑)。1年生のときはいわゆるモラトリアムな時期を過ごしたのですが、2年生になって生物学に興味を持ちました。生物学は勉強すればするほど、摂理がロジカルであることに気づきます。なぜこういう仕組みになっていくのだろうという興味が尽きなかったですね。大学で生物学を専攻することも考えましたが、病気の生物学的な成り立ちを学ぶことにも惹かれ、高校2年生のときに医学部に行こうと思いました。
当時は多くの学生もそうでしたでしょうが、親に相談するということもなく、自分の意志で決めました。
UNICEFに勤務するようになってからも、大学で講義する機会もあるのですが、医学部学生も含め、学部選択の動機が曖昧な大学生が多いと感じています。私たちの時代では、高校3年生の前半までには将来の職業、あるいは方向性をかなり明確に決めていた人が比較的多かったので、時代が大きく変わった印象があります。
筑波大学を選んだのはどうしてですか
長野県でリベラルに育っていたこともあり、昔からのOBがいたり、拘束されるような雰囲気のある古い大学を好まなかったことが大きいです。筑波大学には医局制度がなく、2年生からの専門教育やスーパーローテートする研修ができることも志望した動機でした。事前に大学を訪問する習慣もない時代ですが、父が毎年、成田山にお詣りに行っていたので、「つくばは東京から1時間だ。いいぞ」と勧めてくれたんです。
東京から1時間というと、私のイメージでは八王子でしたが、当時はまだつくばエクスプレスや東京からの直行バスもなく、大町から電車で行ける八王子とは全く雰囲気が違いました。それで受験の日に土浦駅で降りたら、予科練の音楽が流れているし、駅の周囲を暴走族風の車が走り回っていて、カルチャーショックを受けました(笑)。
それは驚きますね
そしてタクシーに乗り、「筑波大に行ってください」と言ったら、運転手さんから「筑波台って、どこの団地だあ」と返ってきましたからね(笑)。私は5期生なんです。まだ地元の人にもつくばに大学ができたことが知られてなかったんでしょう。
私が入学したときにちょうど病院ができたこともあり、施設が整っていなかったので1カ月遅れの5月にスタートしました。それでも1、2期生よりははるかに恵まれていました。1、2期生は皆、長靴とトレーニングウェアで過ごしていたそうです(笑)。
入学されてみて、いかがでしたか
地元の高齢者が話している方言はうまく聞き取れなかったですし、地理的な印象も最初は良くなかったのですが、大学は全く違っていました。教授陣はとても若く、情熱をもっておられる方も多く、大学自体に新しい雰囲気が漲っていました。当時の方針は積極的に学外で修業すべきというもので、筑波大学附属病院の初期研修募集の枠は卒業生の数の半分程度でした。したがって、当時の学生の多くは、学生の頃から将来は外に出ていこうとする意識が高く、現在、日本中の地域で、また政治家から宇宙医学なども含め、色々な分野で活躍している人が多いです。その意味でも筑波を選んだのは良かったですね。
1、2年生は全員学生宿舎で過ごすこともあり、上下関係も厳しくなく、その頃の仲間とは今も付き合いがあります。私は今は医師の仕事をしていないので、最新の治療の分野など分からないところは、同級生によく質問したりもしています。
部活動には入っていらっしゃいましたか
ラグビー部に入っていました。顧問の先生の影響もあり、当時の部員の中でもスポーツドクターになった人が多く、同級生の中には日本代表チームのチームドクターをしていた人もいます。
私も6年間はほとんどラグビーをして過ごしていましたので、我々自身を脳筋肉化症候群と呼んでいました(笑)。
心臓血管外科を選ぶ
専門を心臓血管外科に決めたのはどうしてですか
筑波大学では循環器外科という名称なのですが、あの頃は今とはかなり違って、外科系の方が人気がありました。かっこいいという表現で言えば、心臓血管外科が一番かっこよかったんです。とても忙しいというイメージもありましたが、それもあの時代の価値観としては主流でした。
外科系は運動部に所属していないと採用されないという風潮もあり、運動部での繋がりで入局する人も多かったと思います。でも、心臓血管外科にはそうした運動部的なものはなく、理論的でいわゆる“クール”な雰囲気がありました。私は同様なチームカラーの心臓血管外科と脳神経外科で迷い、最後まで決めきれなかったんです。
でも最終的には脳神経外科に決めて、脳神経外科と書いて提出しようとしたら、そこに同郷の先輩が来て、その場で書き直しをさせられ、心臓血管外科に行くことになりました(笑)。
偶然だったのですね
その先輩は心臓血管外科医ですが、ユニークな経歴を持った人で、旧ソ連の医学部で学び、日本で医師免許を取得され、筑波大学の講師になっていたんです。
そういう経歴な医師も、実力があれば受け入れる当時の教授の姿勢も、最終的に心臓血管外科を選んだ理由の一つでした。
どのような研修医時代をお過ごしになりましたか
最近、現在の初期研修医への指導要領を見て、その細部に検討され、研修医のために考えられたアプローチに驚きました。私たちの頃は、当時はシニアレジデントと呼ばれていた研修3年目の医師が主に指導してくれましたが、それぞれ考えが異なり、手技の標準化や文章化されたマニュアルも、多くの診療科には存在しませんでした。そればかりか、ある診療科のシニアレジデントからは「外科医なら見たらすぐにやれ」と言われ、研修開始2日目から一人で胸腔穿刺をさせられていました。
そのときは担当医の責任と考え、必死でしたが、安全性を無視しており、今では考えられないですよね(笑)。
できないとそれで振り落とされるので、手術や外科的手技の現場では先輩がすることを必死で観察し、あとで外科手技の教科書で確認しながら、自分なりに工夫を加えていました。でも、何かを指示させられてやるより、まずは自分が考えなくてはいけない雰囲気は好きでした。
今の初期研修とは全く違いますね
現在は部下にワーク・ライフバランスを取れ、休みを取れ、取れと口を酸っぱくして言っている立場ですが、私のジュニアレジデント研修2年間は休みがなく、土日以外はほとんどレジデント部屋の椅子を3つ並べ、その上で寝ていました。当時の時代背景として、それが当たり前で、身を粉にして働くことにも意味があったんです。
自分としては医師としての責任感にあふれ、とても充実していました。あの頃を思えば、今の仕事は身体はとても楽です(笑)。
心臓血管外科でどのようなことを学ばれましたか
当時の時代背景として、救命できる手術手技さえ確立されていない、難しい先天性心疾患が多く残っている状況でした。
私は卒後5年目に神奈川県立こども医療センターで後期研修をしましたが、そこで出会った大川恭矩先生にとても憧れました。その先生は今も難病である左心低形成症候群の患者さんに対し、肺血流調整型大川式手術を考案され、おそらく日本で初めて複数の新生児急性期の救命に成功された方です。
後に、根治手術にも成功されまたしたが、偉業にも決しておごることなく、物静かで、常に子どもたちのことを考えられていた医師でした。複雑な手術も、安全に、出血も少なく、かつ短時間で終えるころができれば、多くの子どもたちが手術の次の日に歩けたり、食欲がもりもり回復するのを目のあたりにし、安全で、高い技術を持った外科的介入は子どもたちにとって、とても意味のあることだと思いました。
大学病院とは違ったのですね
子ども病院はやはりその分野のプロフェッショナルの集団でしたね。看護師さんも、経験が豊富なうえに、子どもたちと常に接し、少しの変化も見逃さないような人たちが多かったです。
表現的には「何かいつもと違う」というようなことも、あとで重大なことの予兆であったことも多くありました。
病棟合同カンファレンスでの厳しさも記憶にあります。執刀医ごとの手術時間や出血量も記録され、それらの分析から、看護師長さんに「先生の患者さんには治りが遅い傾向がある」というような厳しい言い方された医師もいました。
他方、子ども病院では、手術室・ICUのチームは皆が自分や他のメンバーが次に何をするべきなのかを分かっているので、執刀医は術野に集中でき、不必要な会話がないので、静かで全てにスムーズなことに気づきました。
チーフレジデントして大学病院に戻ったときにはその経験をもとに、麻酔医や看護師を含めた合同事前カンファレンスにより注意を払い、また常に診療科や卒業年度を超え、チーム全体で術者や主治医の意思や解決すべき課題が共有できるよう、積極的でかつ包摂的なコミュニケーションができるよう、心がけました。
そして、国際貢献に興味を持たれたのですね
新聞紙上で「ハゲワシと少女」の写真を見たことがきっかけです。あの写真を見て、国境や、社会構造、文化の壁を超える仕事をしたいと志したのは一つにはそういう世界を知らなかったことが挙げられます。あのような命と、我々が助けている命の差はないはずだと思ったんです。
我々は一人を助けるのに、ものすごい時間と人員と労力とお金をかけています。その命と彼女のような子どもたちの命の差は何なのかと考えました。
たまたま大学院に行っている頃でしたので、そうした時間が持てたのかもしれません。