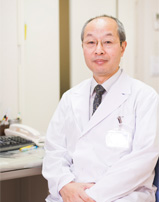腫瘍内科に出会う
がんの内視鏡診断の勉強のために、国立がんセンター中央病院にいらしたのですね。
そうです。内視鏡診断は難しいので、がんセンターに診断学を勉強しに行って、足柄上病院に帰ってくるつもりでした。ところが、がんセンターの内視鏡部に行ってみたところ、非常に面白かったんです。内視鏡検査、内視鏡治療ともに、多くの症例を経験させていただきました。一方で、がんセンターでローテートする研修もさせていただいたんです。レジデントという立場で行っていますので、半人前という感じで、内視鏡部に主軸を置きながら、色々な科を回りました。そこで、消化器内科を回ったときに、大きな出会いがありました。
どなたと出会われたのですか。
室圭(むろ けい)先生です。室先生は現在は愛知県がんセンター中央病院の副院長をなさっているのですが、当時は国立がんセンターにいらして、消化管がんを中心とした薬物療法の専門家でした。その室先生から「これからは内視鏡治療より腫瘍内科の需要が高まるから、転向しなさい」と言われたんです。それで「そうなのかな、自分にも向いているのかも」と、そのまますうっと腫瘍内科に入りました。
そういうきっかけで腫瘍内科に進まれたのですね。
私の国立がんセンターでの同期の中には、最初から腫瘍内科を希望して内科のレジデントをしているという人は大勢いたので、私は彼らとは違う入り方をしました。がんセンターでの内科ローテートを3年間終えたあとで、腫瘍内科医になろうかなと思って、そこで初めて腫瘍内科の道にきちんと入ったので、とても遅いんです。大学を卒業して8年目に転向したことになります。それに、8年目といっても、そのときはチーフレジデントという、腫瘍内科医としては修行の立場でした。その間に研究もしていたので、本格的に腫瘍内科医になって、腰を据えて取り組むようになったのは卒後10年目ぐらいからですね。
腫瘍内科医としての修行をどのように積まれていったのですか。
がんセンターの消化器内科、現在は消化管内科という部署ですが、そこに主軸を置いて、臨床、研究をしていました。その後、医員になってからは消化管内科とともに、外来化学療法科を兼任したんです。外来化学療法科は現在のがんセンターには既になくなってしまったのですが、当時は新しい取り組みとして、がん種を超えて横断的な外来をしましょうという科でした。現在、がんセンターの乳腺・腫瘍内科長でいらっしゃる田村研治先生が科長で、私が唯一の部下でした。
外来をなさっていたのですね。
その頃のがんセンターはレジデントとチーフレジデントで5年間いても、外来をあまりさせてもらえなかったのです。レジデントやチーフレジデントは外来ではなく、入院ばかりを診ていました。当時、既にほとんどが外来に移行していたのだから、入院しか診られないようなシステムでは意味がありません。チーフレジデントが終わる頃にはどのがんの外来もできるというふうにしないといけないということで、消化管内科と兼任ではありましたが、田村先生と一緒に乳がんをはじめ、色々ながん種の患者さんを外来で診たり、カンファレンスで検討したりしていました。私にはそういう珍しいグループのメンバーだった一時期があるのです(笑)。しかし、そのお蔭で、がんの外来化学療法に興味を持つことができましたね。
腫瘍内科を始めて、どのような面白さを感じましたか。
がんの患者さんの中には術前術後の患者さんといった、治る可能性のある方も多くいらっしゃいますが、私たちが相手にしている患者さんは7、8割が治らない患者さんなのです。そういう方々の人生の最後の何年間を伴走することの意義深さや難しさを感じました。それまでの医師生活では出会わなかったことですから、これはじっくり取り組まないといけない分野なのだと思いました。内視鏡治療で治っていく患者さんを送り出すことも重要ですし目指す人も多いですが、腫瘍内科のようなじっくり型の分野を目指す人は少ないかもしれないと考えましたね。このような患者さんとの向き合い方が私の性格に合っていると思えたことは、自分でも新鮮でした。