千葉大学教授になる
それから大学院に進まれたのですね。
本当は循環器医になることに未練があり、かつ、当時学問体系として整っていなかった免疫学の勉強をしたかったので、臨床医を続けながら基礎系大学院に行きたかったんです。そうしたら、医局長から「基礎系大学院に行くのだったら、第一内科を辞めてから行きなさい」と言われたので、すぐに第一内科を辞めました。
コラム・連載
本当は循環器医になることに未練があり、かつ、当時学問体系として整っていなかった免疫学の勉強をしたかったので、臨床医を続けながら基礎系大学院に行きたかったんです。そうしたら、医局長から「基礎系大学院に行くのだったら、第一内科を辞めてから行きなさい」と言われたので、すぐに第一内科を辞めました。
していないです。
オーストラリア・メルボルンにあるWalter and Eliza Hall Institute(WEHI)に留学しました。この研究所は、当時免疫学では世界的に極めて有名なところで、初代の所長はノーベル受賞者Sir. Frank McFarlane Barnetで,「Clonal selection theory of acquired immunity」を提唱した研究者です。その研究所で研究室を構えていて、2018年、Tリンパ球の発見で日本国際賞を受賞したJacques F.A.P Miller先生のところに留学しました。
いいえ。当時の私にはそんな知識はありませんでした。私の恩師である多田富雄先生が「君、ここに行きなさい」とおっしゃったので、「ははあ」と返事しました(笑)。
私は長くいるつもりでしたが、1年2カ月ほど経ったときに、多田先生が「君、帰ってきなさい」とおっしゃったので、「ははあ」と言って帰ってきました(笑)。そのときに多田先生は東京大学教授に転任されました。多田先生がいらした東京大学血清学・免疫学教室はこのほど150周年を迎えた日本で最も歴史のある教室ですが、多田先生がそちらに行かれたので、私は千葉に帰ってきました。
そうです。1980年39歳で教授に就任しました。当時、教授会のメンバーはお年を召された方が大多数でしたので、若造が一人という感じでした(笑)。
いくつかの成果を出していました。そのうちの一つが、免疫の経過とともにB細胞が作る抗体親和性(異物に結合する力)が上昇することに事が知られていましたが、その抗体親和性上昇に、T細胞が関与している事を証明し、Journal of Experimental Medicineに掲載されました。このRockefeller University Pressの雑誌は、100年以上の歴史を持つ医学系雑誌で、過去には野口英世が日本人として初めてこの雑誌に掲載されたことがありましたが、彼に続く2番目の日本人ということになりました。最近は若手の海外留学が減っていることが問題になっていますが、若手研究者にとっては海外に行くことによって、新しい物の見方、新しい概念の糸口を見つけるチャンスなので、若い人に是非、海外留学をおすすめしたいと思います。私も第4の新しいリンパ球NKT細胞を発見する契機となったハイブリドーマ技術を習得したのは留学先のWEHIです。それがなかったら、その後の仕事は多分なかったでしょうね。海外に行くと、日本人が考えないようなことを考える人が大勢いて、良い刺激になります。
オーストラリアから帰ってきて教授になり、「教授としてきちんとした自分の仕事をしないといけないな」と思いました(笑)。多田先生を頼りにして研究するのではなく、自分の研究を確立しないといけない、自分にとって、何が一番大きなクエスチョンなのかを考えました。学生時代と初期の若手研究者時代、私は多田先生の研究テーマである免疫機能を制御するT細胞を研究していました。そこで得た知識は、免疫系の中でもT細胞は様々な機能を発揮するため、面白い細胞だということでした。
免疫反応を上げる機能・免疫反応を起こすヘルパーT細胞と、免疫反応を抑制するT細胞とが免疫系機能をバランス良く調節し、シーソー状態になって機能しています。たとえば、アレルギーと感染症に関わる免疫はまさしくシーソーの関係にあり、相反するT細胞機能によってコントロールされていて、普段から軽い感染症に曝されているヒトはアレルギーにならない。一方、乳児期に大量の抗生剤を投与されたヒトはアレルギーを発症しやすいことなどです。
T細胞が免疫状態を大きくコントロールしているのだとすると、免疫機能の詳細を理解するためにはT細胞を集団で見るのではなく、一つ一つのT細胞機能を解析する必要があると考えました。しかし、今でこそSingle Cell Biologyが盛んですが、リンパ球を一つ一つ見る技術は、当時は不可能に近いことだと思っていました。それを可能にする唯一の技術が「細胞融合技術」でした。これはすでに大阪大学の岡田善雄先生が「センダイウィルス」を使って行っていました。
センダイウィルスを感染させ、細胞同士を融合させる手法です。このウイルスは発見者の石田名香雄教授がおられた東北大学にちなんで、「センダイウィルス」と呼ばれていましたが、血球凝集性からHemagglutinating Virus of Japan(HVJ)とも呼ばれています。したがって、細胞融合法の基本原理は日本人である岡田先生による発見でしたが、のちに、スイスBasel免疫学研究所Georges KohlerとCesar Milstienが、ウイルスの代わりにポリエチレングリコールを用い、さらにHGPRT(hypoxanthineguanidine-phosphoribosyltransferase)酵素欠損腫瘍細胞株とリンパ球と融合させることにより、融合した細胞だけを増殖させるHAT(hypoxanthine-aminopterin-thymidine)セレクション法を考案し、1個のリンパ球を増殖させる技術開発を行ったため、抗体を作るなどの医学応用に多く利用され、ノーベル賞受賞に繋がりました。この技術のオリジナリティを持つ岡田先生はノーベル賞を受賞していません。この原因の一つは、この技術を最初に発表したのが大阪大学雑誌だったからではないかと言われています。インターナショナルな場で、しかも英語で発表すべきだったのに、ローカルな雑誌に発表してしまい、ノーベル賞受賞を逸してしまったのは誠に残念でした。余談ですが、これは北里柴三郎にも言えることです。日本人第一号のノーベル賞は北里柴三郎だったはずですが、共同研究者のベーリングが受賞したのに、ローベルト・コッホ研究所でその研究を主導し、日本での実績もあった北里が受賞できなかったのは当時の日本の国際的な立場も反映しているとも言われています。
Georges KohlerとCesar Milstienが開発したB細胞ハイブリドーマ技術で単一細胞を増殖させる技術をオーストラリア留学中に習得し、帰国後、それをT細胞に応用し、Tリンパ球機能解析に用いることにしました。この方法を利用すれば、一つ一つの異なるT細胞の機能を見ることができると考えました。細胞表面分子の特徴や、どういう分子が発現すると、どのような機能を発現できるかを知ることができます。
私は脾臓T細胞の中から抗原特異的T細胞集団を分離した後、それらを用いて細胞融合実験を13回繰り返して、独立で作った免疫制御機能を持つハイブリドーマを全て解析しました。最初に抗原を認識する受容体は何を使っているのかを調べました。そのときは今みたいに遺伝子解析技術が進んでいなかったので、サザンブロト法(※1)という、複数の制限酵素(※2)でハイブリドーマDNAを切断し、その後受容体遺伝子断片がどのように寒天内で移動するかを電気泳動法で見ることにより、受容体遺伝子の種類を判定する方法を採りました。異物と結合する部分の受容体部分に注目すると、一兆種類あると予想される免疫系抗原受容体ですから、当然、受容体部分をコードする遺伝子部分は配列が異なるので、制限酵素で切ると、リンパ球ごとの受容体遺伝子断片の長さ、すなわち、寒天内で検出できる受容体遺伝子断片サイズは全て違うものと予想されました。ところが、13種類のハイブリドーマから検出された受容体遺伝子は驚いたことに全部、同じパターンでした。異なる3種類の制限酵素を試しても、全く同じパターンで、免疫学の常識とは異なる結果で、不思議でした。13回も別々に作ったリンパ球の受容体が全て同じというのは、当時の免疫学の常識では説明できない、新しい免疫システムが存在するのではないかと興奮しました。多くの人は、それをhybridoma artifactだと言って相手にしませんでした。しかし、これが「常識とは違う」ことを発見した瞬間です。
既成概念とは違う、常識と違う現象を発見したときには大発見があります。これは常に若い人に言っていることです。ところが、今の若い人は、謙虚で、まずは自分が間違っているのではないかと思う人が多いですね。
研究の世界では謙虚では困ります(笑)。
私も自分を守っていないわけではないですよ(笑)。まずは、その常識外れの現象を検証することです。本当に間違っていないかを検証すると同時に、わくわくしながら「これがこうだったら、こうしよう」と、思うことが楽しみですね。常識外れの現象を発見したときには、大発見の前ぶれであると。私は13回ハイブリドーマを作成しているので、実験事実に関しては確信がありましたが、ある特殊な免疫細胞をピックアップしたのではないかという思いがありました。そこで、受容体遺伝子クローニングをして、確認することにしました。
もっと驚きがありました。利根川先生が発見したリンパ球抗原受容体一兆種類のレパートリーを作るメカニズムは遺伝子再構成と呼ばれ、すべての遺伝子は親から引き継がれることが常識だった当時の遺伝子発現機序を覆すものでした。すなわち、リンパ球受容体遺伝子の場合、親から受け継がれる遺伝子は完成型の遺伝子ではなく、受容体遺伝子を構成する遺伝子断片群(V遺伝子断片群とJ遺伝子断片群)だけが子どもに引き継がれ、その後、リンパ球が発生する段階で、自前でVとJ遺伝子断片群の間で、ランダムに組み合わせが起こり、一つの完成型受容体遺伝子を作るというものです。リンパ球発生段階で、受容体遺伝子断片のランダムな組み合わせと、VJ遺伝子断片の再結合のときに生ずるランダムなDNA塩基の挿入が起こるため、無限のレパートリーを作ることが可能になります。
しかし、私の場合、13個のハイブリドーマからクローニングした受容体遺伝子はVα14とJα18という遺伝子の組み合わせだけから作られている受容体遺伝子で、しかも、このVとJの間にランダムな遺伝子挿入により、アミノ酸配列の異なる膨大な受容体遺伝子ができるはずでしたが、不思議なことに13個のハイブリドーマ全ては、VJ結合部は一塩基だけが挿入されており、その部分はグリシンをコードする第三塩基に当たるため、どんな塩基が挿入されても、全て同じ均一なアミノ酸配列の受容体遺伝子で、常識では考えられないことでした。
通常、ランダムに選ばれたVとJ遺伝子が結合するときには、選ばれたVJ遺伝子の間にあるDNAはループ状に切断され、その後、切れたVJ遺伝子間を繋ぐためにランダムにDNAを挿入して、完成型の受容体ができますが、その部分はちょうど抗原を認識する配列になるために予想もしない異物を認識することが可能となります。この受容体遺伝子の部分はもともと青写真にはない部分なのでN領域(non-coding)と呼んでいます。だから、N領域は受容体レパートリーを増やすのに役立っていますが、私どもがクローニングしたものはVとJの間は1個の塩基しか入っていないため、極めて異常なことであり、「常識とは違う」ことを発見したのです。どうしてそうなったかは、あとで判明します。ここでも、遺伝子再構成はランダムイベントであるという常識を覆す現象、1)V14とJ18遺伝子は、DNA立体構造上近傍にあり結合し易い上に、2)挿入されるDNA塩基は限られており、3)この受容体はNKT細胞だけに発現され、4)NKT細胞が分化・増殖する過程でN領域の一塩基挿入の受容体を持つNKT細胞だけが選択的に選ばれたためと判明しました。
著者プロフィール

元 国立研究開発法人理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター長
1940年新潟県長岡市生れ。
1967年千葉大学を卒業後、循環器医を目指して1年間のインターン中に心臓カテーテルを実習し、千葉大学医学部第一内科に入局するも、関連病院での入院患者日本第3例目のマクログロブリン血症患者の受け持ち医になったのを契機に、免疫学を勉強するために1968年大学院に入学
1974年千葉大学大学院医学研究科を修了すると同時に、日本で初めて千葉大学に設置された免疫学研究センター助手に就任する。
その後、オーストラリア、メルボルンにあるウォルター&エリザ・ホール医学研究所に留学。
1980年千葉大学医学部免疫学教授に就任する。
1986年NKT細胞を発見し、1997年NKT細胞リガンドが糖脂質であることを発見するとともに、その生体防御機能、免疫制御機能を明らかにする。
1996年から2000年まで千葉大学医学部長を務める。
また、1997年から1998年まで日本免疫学会会長を務める。
2001年に特殊法人理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター長に就任する。
2013年独立行政法人理化学研究所統合生命医科学研究センター特別顧問兼グループディレクター。
2018年から国立研究開発法人理化学研究所科技ハブ産連本部創薬・医療技術基礎プログラム臨床開発支援室で客員主管研究員を務める。
Nature、Scienceをはじめ400編以上の論文を執筆。
ベルツ賞1977、野口英世記念医学賞1993、上原賞2004、紫綬褒章2004、瑞宝中綬章2016受賞。
また、2000年には日本国際賞委員長として、天皇・皇后両陛下に免疫・アレルギーの特別講義を行った
2014年米国免疫学会は、免疫学の進歩に貢献したとして、“NKT細胞発見” を “Pillars of Immunology” の一つに認定した。
 精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
 がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
 医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
 私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
 次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
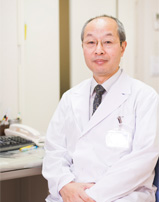 若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長
若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長