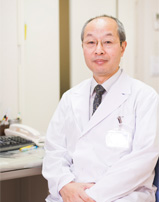自然免疫と獲得免疫の両方を活性化
NKT細胞が、自然免疫と獲得免疫の両方を活性化させることについて、伺えますか。
NKT細胞の女王蜂機能は、感染症とがんの制御には必須です。NKT細胞の「長期免疫記憶を作る」「免疫抑制マクロファージを排除する」「未熟樹状細胞を成熟樹状細胞に成熟させる」こと、それに「アジュバント作用」が重要です。これらの機能において、がんと感染症で大きく異なる点は、病原体は病原体としての固有の抗原のほかに、NKT細胞を活性化するアジュバント物質を持っていいますが、がんにはありません。したがって、がんの場合には人工的にNKT細胞を活性化しないと機能を発揮できませんが、病原体感染の場合は、NKT細胞を人工的に活性化しなくとも、自然に機能を発揮できます。アジュバント作用の原理は大阪大学審良静男教授たちが研究している自然免疫受容体に病原体アジュバント物質が作用すると、そのシグナルが自然免疫系細胞を活性化し、IL−12サイトカイン産生を誘導し、そのIL-12が、NKT細胞を活性化し、インターフェロンガンマの産生を促し、自然免疫系NK細胞や獲得免疫系の抗原刺激を受けた免疫細胞の活性化、クローン性の増殖・機能発現を誘導します。活性化される免疫細胞の場合は、抗原刺激を受けインターフェロンガンマ受容体を発現している免疫細胞ですので、無駄なく、抗原特異的集団、標的を認識した細胞だけが一気に増殖できる仕組みです。普通の抗原刺激だけだと数倍になるのに何日もかかるのに、NKT細胞が一緒にいると、何と1週間から10日の間に何百万倍にも増えます。NKT細胞がいないと、あと押ししてくれる人がいないから、増やすこともできませんが、女王蜂戦略では、子どもたちを次々に送り出すことができますので、継続的ながん治療が可能になります。
がんの治験が始まっているとのことですが、どういった内容なのですか。
今申し上げたように、がんを治療する場合のポイントは、がん細胞自身にNKT細胞を活性化するアジュバント物質がないので、NKT細胞を人工的に活性化させることが必要です。そこで、単に糖脂質NKT細胞リガンドだけを注射すれば、生体内にNKT細胞を活性化できるのではないかと考え、リガンド単体の投与実験を行いましたが、やはり低分子を注射しただけではでうまくいきませんでした。うまくいかない理由の一つは糖脂質の構造です。糖脂質は親水性の糖が頭にあって、疎水性の脂質が支えています。糖の部分は親水基で水に馴染むので溶けている状態になりますが、脂質の部分は水をはじく疎水性部分です。すると、この疎水性部分で疎水結合が起こり、糖脂質がミセル状の塊になってしまい、血中に投与しても思うところにデリバリーできないので、うまくいきません。そこで、自分の細胞に糖脂質をくっつける方法、すなわち、細胞表面にある「お盆」の上に載せてあげれば、NKT細胞糖脂質リガンドが正常状態と同じく機能を発揮できると考えました。したがって、お盆つきの細胞にNKT細胞リガンドが結合した細胞を作って、身体に投与する「人工的にNKT細胞を活性化するお薬」として用いています。
今はその途中なのですね。
ええ。「再生医療等製品」にするための、人への安全性・有効性を検証するためのプロセスで、慶應義塾大学でスタートしているところです。
どうして慶應義塾大学なのですか。
理化学研究所と慶應義塾大学は包括協定を結んでいるのです。理化学研究所は病院がありませんので、「基礎研究の成果を世の中に出す」ことが最大のテーマになった場合、慶應義塾大学のような橋渡し研究支援拠点として、自分の所以外のシーズを積極的に採用して、人体に応用するいわゆる治験を実施していただける大学は貴重で、実に助かります。
アレルギーの研究
先生はアレルギーも研究なさっていますね。
アレルギーと感染症やがんはちょうど対局にあります。アレルギーと感染症は免疫系T細胞機能が相互に調節し合う、あたかもシーソーの状態にあるので、感染に対応するTh1細胞が増えれば、アレルギーを誘導するTh2細胞が減ります。逆に、感染がなくなるとTh1細胞が用無しになるので、Th1細胞は減り、逆にTh2細胞が増え、アレルギーが増えます。だから汚くしている方がアレルギーにはなりません。青っ洟を垂らしている子、慢性感染症がある子はアレルギーにはなりません。今はそういう子どもを見ませんが、私たちの時代は皆、そうでした。洟を学生服の袖で拭うものですから学生服の袖がピカピカしていましたよ(笑)。だから、戦前の年代にはアレルギーは少ない。
先生が注目されたのはどういったことですか。
NKT細胞は、感染症制御には必須の細胞です。アレルギーと感染症はシーソーの関係にあるので、NKT細胞が活性化状態だと、どうしてアレルギーが減るのかという疑問です。感染症の場合にはNKT細胞からのインターフェロンガンマがTh1細胞を活性化するのに重要であると、分かっていましたので、他のどの様なサイトカインが出るとアレルギーが抑制されるのか、アレルギーの根源であるIgE抗体産生に変化を与えているのはどの様なサイトカインなのか調べることにしました。調べるうちに、NKT細胞が産生するIL-21というサイトカインが、NKT細胞抗原刺激時に上昇し、IgE産生は逆に抑制される事を発見しました。そのIL-21サイトカインは、アレルギーを起こすIgE-B細胞だけを選択的に殺すことが分かったのです。感染防御に重要なIgGを作るIgG-B細胞には全く影響を与えませんでした。それでIL-21によるIgE B細胞を殺す仕組みを開発すれば、アレルギーワクチンになるだろうということで、今はその研究を行っています。そのメカニズムは、NKT細胞からのIL-21が、IgE-B細胞のIl-21受容体に結合し、そのシグナルが、細胞死を誘導するBmf分子のリン酸化を促進し、細胞死を誘導するというものです。感染防御にかかわるIgG−B細胞は、細胞死を誘導するリン酸化Bmf分子の量が極めて少なく、細胞死を誘導しないことから、感染症には無害で、アレルギーだけを選択的に抑制することが判明しました。
IgEがなくなるかもしれないのですね。
この治療によってIgEが我々の体から消えてなくなると、どうなるのか心配で、多くの方々に「そもそもIgEはどういうときに役に立っているのですか」と聞かれることがあります。IgEはもともと寄生虫を排除する寄生虫感染に対しての防御反応の役割を持っていたのです。でも、今の世の中では寄生虫に感染するということはほとんどありませんので、IgEがなくなったとしても、現代人は別に困りません。ある抗原に特異的なIgEを抑制するのではなく、全IgE産生を抑制することができるので、どんなアレルギーの病気でも治療することができるようになる、そういうお薬です。
今の時代にどんなアレルギーでも治療できるというのはすごいことですね。
億万長者になりますね(笑)。
日本人は花粉症の人が多いですしね。
原理としては明快ですし、動物実験ではIgE産生が抑制され1/10以下になります。同じ原理、すなわちIgE抗体産生をIL-21で抑制するものにBCGワクチンがあります。実際アレルギー患者さんにBCGを接種すると血中IgEはドラマチックに下がりましたので、NKT細胞リガンドを用いてアレルギーを治療する時代が来ると思います。
アレルギーの世界が全く変わるかもしれませんね。
そうなってくれると、有り難いですね。
英語論文
日本人にとって英語で論文を書くのはハードルが高いと言われています。
実際はそうですが、科学英語は基本的には中学生の英語でいいのです。高い表現力がなくても、パターンが分かれば、論文は書けるのです。その「取っ掛かり」を教えてもらう機会があれば良いのです。一つは外国に行くことですね。何も分からなかったとしても、とにかく英語に慣れることができます。
大学勤務の先生方は英語で論文を書くことが義務づけられたので、倍ほどの時間がかかるとおっしゃっている方もいます。先生の読み方、書き方のポイントを教えてください。
論文の読み方、書き方があります。最初から細かいところまで全て読もうとすると、ストーリーが頭に残らず、理解できません。人に説明するつもりで読む事が重要です。まず、サマリーを読み、それから図についている説明を読みます。それで、ほとんど分かるはずです。あとはディスカッションのところを飛ばし読みすれば、全体を理解することができます。図の説明を読めば、サマリーに書いてあることを事実として理解できるわけですから、そこはきちんと読めばいいのです。後は、ディスカッション部分を読んで、実験結果のポイントを理解すれば完璧です。
書き方に関してはいかがですか。
論文構成は、サマリーがあり、続いてイントロダクション、マテリアルズ&メソッド、リザルト、ディスカッション、引用文献の順に記載されています。しかし、書くときはリザルトおよび結論であるサマリーから書きます。仕上がっている順番通りに書くのではありません(笑)。マテリアルズ&メソッドは、通常実験中から書き始めるものです。
逆算するということですか。
そうです。先ずリザルトを書き、その結果に応じたディスカッションを書きます。それが終わったら、イントロダクションを書きます。すなわち、イントロダクションは、リザルト・ディスカッションから誘導されるのもので、なぜこの研究が必要かを説明するためのものです。そうしないとロジックが繋がりませんから、読んでいる人が何を問題にしているのかを理解できません。また、各項目を書くときには、予め記載すべき事を日本語で箇条書きにしておき、ロジックが通っているか吟味します。我々日本人は、英語でロジックを考える習慣がありません。日本語でしかロジックを考えられないからです。
ロジックがずれないようにしないといけないですね。
リザルトとディスカッションを全て書いてから、イントロダクションを書けばいいのです。しかし、そういうことを教える人がいないと、習得は難しいですね。論文の書き方を教えるのも先輩の責任だと思います。
著者プロフィール

著者名:谷口 克(まさる)
元 国立研究開発法人理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター長
1940年新潟県長岡市生れ。
1967年千葉大学を卒業後、循環器医を目指して1年間のインターン中に心臓カテーテルを実習し、千葉大学医学部第一内科に入局するも、関連病院での入院患者日本第3例目のマクログロブリン血症患者の受け持ち医になったのを契機に、免疫学を勉強するために1968年大学院に入学
1974年千葉大学大学院医学研究科を修了すると同時に、日本で初めて千葉大学に設置された免疫学研究センター助手に就任する。
その後、オーストラリア、メルボルンにあるウォルター&エリザ・ホール医学研究所に留学。
1980年千葉大学医学部免疫学教授に就任する。
1986年NKT細胞を発見し、1997年NKT細胞リガンドが糖脂質であることを発見するとともに、その生体防御機能、免疫制御機能を明らかにする。
1996年から2000年まで千葉大学医学部長を務める。
また、1997年から1998年まで日本免疫学会会長を務める。
2001年に特殊法人理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター長に就任する。
2013年独立行政法人理化学研究所統合生命医科学研究センター特別顧問兼グループディレクター。
2018年から国立研究開発法人理化学研究所科技ハブ産連本部創薬・医療技術基礎プログラム臨床開発支援室で客員主管研究員を務める。
Nature、Scienceをはじめ400編以上の論文を執筆。
ベルツ賞1977、野口英世記念医学賞1993、上原賞2004、紫綬褒章2004、瑞宝中綬章2016受賞。
また、2000年には日本国際賞委員長として、天皇・皇后両陛下に免疫・アレルギーの特別講義を行った
2014年米国免疫学会は、免疫学の進歩に貢献したとして、“NKT細胞発見” を “Pillars of Immunology” の一つに認定した。