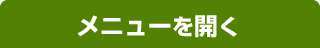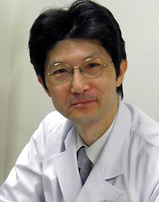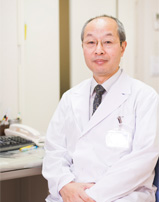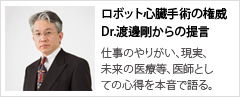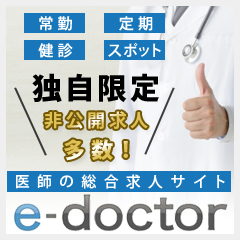第90回
臍帯血バンク
 前回までは、長々と妊活について触れてきた。まあ、何故不妊治療を始めたかの理由は以前述べた通りなのだが。実際、待ち望んだ子供ができた方達には末期癌が治癒した方と同じくらい喜んでもらえる。もちろん喜びの内容は多少違うけど。これは比較するものではないのだが。それに、もう一つの動機としては、私のアプローチが従来の不妊治療では、案外盲点になっているところに対するものだからだ。どうゆう事か?前回までの解説で何となく気づかれたかと思うが、卵子と精子が問題なく、さらに体外受精させたりなどの治療には全く触れていない。
前回までは、長々と妊活について触れてきた。まあ、何故不妊治療を始めたかの理由は以前述べた通りなのだが。実際、待ち望んだ子供ができた方達には末期癌が治癒した方と同じくらい喜んでもらえる。もちろん喜びの内容は多少違うけど。これは比較するものではないのだが。それに、もう一つの動機としては、私のアプローチが従来の不妊治療では、案外盲点になっているところに対するものだからだ。どうゆう事か?前回までの解説で何となく気づかれたかと思うが、卵子と精子が問題なく、さらに体外受精させたりなどの治療には全く触れていない。
不妊症全体の約20%は卵子と精子に問題が無いのに妊娠しない原因不明不妊娠とされている。さらに体外受精(IVF)の場合、正常受精した胚を移植しても約50% は着床に至らないとされている。結局のところトータル的に見ると、不妊の殆どが「原因不明不妊娠」なのだ。確かに、受精卵が育たない原因の50%~80%は染色体異常と言われているが、残りの受精卵が育たない原因ははっきりしていない。
つまり、卵子、精子の活性の源であるミトコンドリアの賦活や子宮環境、免疫異常などによる排除などに対する有効なアプローチがなされていないのだ。
逆に、ここをしっかりフォロー出来れば、かなりの「原因不明不妊娠」が改善できる可能性が高い。実際、いわゆる妊娠条件の悪い方々でも妊娠されている方々がいる。
と、まあ今後不妊についてもアプローチしていくつもりだ。経過はそのうちにで、乞うご期待。
意外に思われるが、不妊治療にかなり精力を割いたので、後書きのようなものが長々となってしまった。
 で、本来なら今回は再生医療のお話をしようと思っていた。前に「臍帯血バンク」再開の話がチラッと出たのだが、その後の顛末について。
で、本来なら今回は再生医療のお話をしようと思っていた。前に「臍帯血バンク」再開の話がチラッと出たのだが、その後の顛末について。
だいたい「○○バンク」と称する物をつくるとき、最も重要なのはなんだと思います?検体を処理した上で長期保存する技術?それに伴う事務関係の構築?どれも重要でノウハウの塊なんだが、これらについては以前やっていたからそれなりにツテがあるので、機材や施設は何が必要かや扱っている業者さんもわかっているし、処理方法なんかもプロトコールあるから比較的すぐに整えられる。経験の無い技師(一般人ではチョと無理だが)でもちょっと教えればできる。
最も重要なのは検体の確保のですよ。こればかりは一気にはできない。協力してもらう産科病院を見つけ、現場の医師やナースに説明して、協力をお願いしなければならない。妊婦さんへの説明も兼ねて現場の医師達にお任せなのだ。院長、事務長は歓迎してくれても、現場にしたら下手したら修羅場になるかもしれないお産の最中に余計な仕事増やされるわけだから歓迎される訳がない。と言うわけで、営業と言うか、この辺りの交渉が大変で、実際どう言う手順で検体を輸送するかも打ち合わせなければならない。さらに基本的に検体採取後24時間以内に処理しないといけないので、遠方(だいたい車で行けない範囲)からの施設だと航空便の時間や深夜に空港で受け取る場合のラボまでどう運ぶかの体制を構築しないといけない。しかも365日24時間だ。お産はいつ始まるかわからないからね。
 もう一つの大きな問題として、日本で「臍帯血バンク」を作るのは可能だが、現行どのような状況なのか把握しないといけない。法的に規制がなくとも、各方面にお伺いを立てないといけないかも知れない。日本特有の状況だけどね。後でクレーム付けられたりすると面倒だからね。更に臨床利用するためは「認可」という高いハードルが存在する。
もう一つの大きな問題として、日本で「臍帯血バンク」を作るのは可能だが、現行どのような状況なのか把握しないといけない。法的に規制がなくとも、各方面にお伺いを立てないといけないかも知れない。日本特有の状況だけどね。後でクレーム付けられたりすると面倒だからね。更に臨床利用するためは「認可」という高いハードルが存在する。
このように書いていくと、「無理なんじゃない?」と思われるだろう。そりゃそうだ、元々認可が降りないものだから色々と作戦を練って行かないと。
そこでだ。まず、ラボをはじめ貯蔵施設を作るのは資金さえあれば比較的簡単なのだ。しかし問題は何処に作るかだ。交通の便で言うと東京周辺に作るのが望ましい。しかし、後で述べるが、検体をどこから採取するかだ。大手の運送会社が対応している時間帯なら何処でもあまり関係ないだろうが。配送時間外の場合、新幹線で運ぶのか、航空便で運ぶのかで違ってくる。一方で今後の運用を考えると「医療特区」内につくるというのも、重要な選択肢の一つだし。
 もう一つの難題は、何処と協業ないし、はなしをつけながらすすめるかだ。お役人相手だと、「ダメ」に決まってるし、「○○学会」と言っても、内部の利権構造がややこしい上に、実際何かの権限があるわけでもない。以前も、それがややこしくて、海外で脳性麻痺の治療していたわけだし。
もう一つの難題は、何処と協業ないし、はなしをつけながらすすめるかだ。お役人相手だと、「ダメ」に決まってるし、「○○学会」と言っても、内部の利権構造がややこしい上に、実際何かの権限があるわけでもない。以前も、それがややこしくて、海外で脳性麻痺の治療していたわけだし。
まあこれらの難題をどうしたかは次回で。ちょっと衝撃の結末に乞うご期待。
著者プロフィール
 Dr.中川 泰一
Dr.中川 泰一
中川クリニック 院長
1988年関西医科大学卒業。
1995年関西医科大学大学院博士課程修了。
1995年より関西医科大学附属病院勤務などを経て2006年、ときわ病院院長就任。
2016年より現職。
- Dr.中川泰一の
医者が知らない医療の話 - 90. 臍帯血バンク
- 89. マクロファージと不妊治療-IV
- 88. マクロファージと不妊治療-III
- 87. マクロファージと不妊治療-II
- 86. マクロファージと不妊治療-I
- 85. 中国での幹細胞治療解禁
- 84. 過渡期に入った保険診療
- 83. 中国出張顛末記Ⅲ
- 82. 中国出張顛末記Ⅱ
- 81. 中国出張顛末記
- 80. 保険診療と自由診療
- 79. マクロバイオームの精神的影響について
- 78. マクロバイオームの遺伝子解析Ⅲ
- 77. マクロバイオームの遺伝子解析Ⅱ
- 76. 中国訪問記Ⅱ
- 75. 中国訪問記
- 74. 口腔内のマクロバイオームⅡ
- 73. 口腔内のマクロバイオーム
- 72. マクロバイオームの遺伝子解析
- 71. ベトナム訪問記Ⅱ
- 70. ベトナム訪問記
- 69. COVID-19感染の後遺症
- 68. 遺伝子解析
- 67. 口腔内・腸内マクロバイオーム
- 66. 癌細胞の中の細菌
- 65. 介護施設とコロナ
- 64. 訪問診療の話
- 63. 腸内フローラの影響
- 62. 腸内フローラと「若返り」、そして発癌
- 61. 癌治療に対する考え方Ⅱ
- 60. 癌治療に対する考え方
- 59. COVID-19 第7波
- 58. COVID-19のPCR検査について
- 57. 若返りの治療Ⅵ
- 56. 若返りの治療Ⅴ
- 55. 若返りの治療Ⅳ
- 54. 若返りの治療Ⅲ
- 53. 若返りの治療Ⅱ
- 52. ワクチン騒動記Ⅳ
- 51. ヒト幹細胞培養上清液Ⅱ
- 50. ヒト幹細胞培養上清液
- 49. 日常の診療ネタ
- 48. ワクチン騒動記Ⅲ
- 47. ワクチン騒動記Ⅱ
- 46. ワクチン騒動記
- 45. 不老不死についてⅡ
- 44. 不老不死について
- 43. 若返りの治療
- 42. 「発毛」について II
- 41. 「発毛」について
- 40. ちょっと有名な名誉教授とのお話し
- 39. COVID-19と「メモリーT細胞」?
- 38. COVID-19の「集団免疫」
- 37. COVID-19のワクチン II
- 36. COVID-19のワクチン
- 35. エクソソーム化粧品
- 34. エクソソーム (Exosome) − 細胞間情報伝達物質
- 33. 新型コロナウイルスの治療薬候補
- 32. 熱発と免疫力の関係
- 31. コロナウイルス肺炎 III
- 30. コロナウイルス肺炎 II
- 29. コロナウイルス肺炎
- 28. 腸内細菌叢による世代間の情報伝達
- 27. ストレスプログラム
- 26. 「ダイエット薬」のお話
- 25. inflammasome(インフラマゾーム)の活性化
- 24. マクロファージと腸内フローラ
- 23. NK細胞を用いたCAR-NK
- 22. CAR(chimeric antigen receptor)-T療法
- 21. 組織マクロファージ間のネットワーク
- 20. 肥満とマクロファージ
- 19. アルツハイマー病とマクロファージ
- 18. ミクログリアは「脳内のマクロファージ」
- 17. 「経口寛容」と腸内フローラ
- 16. 腸内フローラとアレルギー
- 15. マクロファージの働きは非常に多彩
- 14. 自然免疫の主役『マクロファージ』
- 13. 自然免疫と獲得免疫
- 12. 結核菌と癌との関係
- 11. BRM(Biological Response Modifiers)療法
- 10. 癌ワクチン(樹状細胞ワクチン)
- 09. 癌治療の免疫療法の種類について
- 08. 食物繊維の摂取量の減少と肥満
- 07. 免疫系に重要な役割を持つ腸内細菌
- 06. 肥満も感染症? 免疫に関わる腸の話(2)
- 05. 肥満も感染症? 免疫に関わる腸の話(1)
- 04. なぜ免疫療法なのか?(1)
- 03. がん治療の現状(3)
- 02. がん治療の現状(2)
- 01. がん治療の現状(1)
-
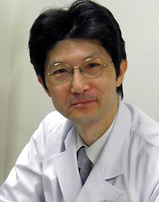 精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
精神科医とは、病気ではなく人間を診るもの
井原 裕Dr.
獨協医科大学越谷病院
こころの診療科教授
-
 がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
がん専門病院での研修の奨め
木下 平Dr.
愛知県がんセンター
総長
-
 医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
医学研究のすすめ
武田 憲夫Dr.
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
院長
-
 私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
私の研究
一瀬 幸人Dr.
国立病院機構 九州がんセンター
臨床研究センター長
-
 次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
次代を担う君達へ
菊池 臣一Dr.
福島県立医科大学
前理事長兼学長
-
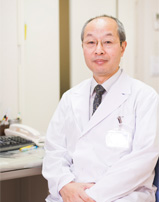 若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長
若い医師へ向けたメッセージ
安藤 正明Dr.
倉敷成人病センター
副院長・内視鏡手術センター長