香港返還直後の1997年7月にアジア通貨危機が始まった。ヘッジファンドの空売り攻撃を受け、東南アジアの主要通貨が急落。東アジアの通貨も動揺し、世界の金融市場に緊張が走った。1997年10月に入ると、ヘッジファンドの矛先は返還されたばかりの香港に向いた。しかし、香港はヘッジファンドの攻撃を退け、通貨防衛に成功する。
香港が通貨防衛に成功した理由を理解するには、香港ドルという通貨のメカニズムを知ることが不可欠だ。しかし、通貨は多くの人々にとって身近な存在であるものの、そのメカニズムを知る人は少ない。
そもそも日本円の仕組みさえ知らない日本人が、香港ドルのメカニズムを理解できるはずもない。そこで今回は最初に日本円の仕組みを解説する。そのうえで、香港ドルの特性を紹介し、通貨防衛に成功した理由を探る。
管理通貨制度と本位制度
 日清戦争の講和会議が開かれた山口県下関市の春帆楼
日清戦争の講和会議が開かれた山口県下関市の春帆楼
金貨2.3億両の賠償金を準備資産に、日本は金本位制に移行
現在の世界を見渡すと、多くの国や地域が“管理通貨制度”を採用。管理通貨制度が広く採用される前は、“本位制度”の時代であり、金本位制や銀本位制などが存在した。
本位制度の通貨は“本位貨幣”(本位通貨)と呼ばれる。通貨の発行量は、“正貨”である金や銀の準備高に拘束される。いわゆる紙幣である銀行券は、正貨である金や銀との交換が可能な“兌換紙幣”として発行された。
しかし、現在の世界で一般的な管理通貨制度では、通貨の発行量は拘束されない。その通貨は政府への信頼で成り立つため、“信用貨幣”(信用通貨)という。管理通貨制度の紙幣は、正貨との交換が保障されない“不換紙幣”であり、“信用紙幣”とも呼ばれる。
信用貨幣の仕掛け
本位貨幣は正貨との引換券のようなものであり、その価値は現物の金や銀で裏付けられている。一方、信用貨幣にはそうした裏付けはない。それなのに決済手段として流通する背景には、“発行者の財務の健全性”、“通貨価値の安定”、“強制通用力”という三つの仕掛けがある。
財務的に不健全であり、倒産の可能性があるような機関が発行する通貨は、誰からも信用されない。それゆえ“発行者の財務の健全性”が重要だ。発行者が倒産すれば、その通貨を発行した責任者がいなくなるわけであり、人々に大きな不安をもたらす。
また、通貨の価値が不安定となり、「昨日は紙幣1枚でリンゴが10個も買えたが、今日は同じ紙幣1枚を差し出しても、1個しか買えない」という状況が続くなら、誰もその通貨を受け取ろうとしない。それゆえ、“通貨価値の安定”が必要だ。その手段として通貨の発行者は、発行量や流通量を調節しなければならない。
その通貨の法的位置づけが曖昧なら、誰も受け取ろうとしない。それゆえ、その通貨の地位を法律に明記したうえ、決済手段として使うよう強制する必要がある。こうして通貨に与えられた力を“強制通用力”という。強制通用力を有した通貨は“法定通貨”と呼ばれる。
“手で触れる通貨”と“眺めるだけの通貨”
 国立印刷局で印刷される日本銀行券
コロナ禍による経済へのダメージや日本の財政問題をめぐり、「お金をジャンジャン刷れば良い」という言説が最近よく聞かれる。有名人がそうしたことを言うため、それを信じ込む人も多い。ただ、そうした言説を唱える人は、中央銀行の通貨発行メカニズムなどを知らないのだろう。知っていれば、そうした言説を唱えるなど到底できない。
国立印刷局で印刷される日本銀行券
コロナ禍による経済へのダメージや日本の財政問題をめぐり、「お金をジャンジャン刷れば良い」という言説が最近よく聞かれる。有名人がそうしたことを言うため、それを信じ込む人も多い。ただ、そうした言説を唱える人は、中央銀行の通貨発行メカニズムなどを知らないのだろう。知っていれば、そうした言説を唱えるなど到底できない。
お金は身近な存在であり、それは紙幣や硬貨というかたちで、誰もが知っている。そのため、お金はすべて印刷されたり、鋳造されたりするものだと思い込んでいる人が多い。だが、実際はそうではない。
いわゆる通貨には、紙幣や硬貨などの“現金通貨”のほかに、帳簿上の数字として存在する“預金通貨”の二種類がある。多くの人が自己の金融資産として保有している通貨にも、財布に入っている現金通貨のほか、口座に入っている預金通貨の二つがある。
そうした身近な個人資産の内訳を見ると、手で触れる現金通貨よりも、眺めることしかできない預金通貨の方が、金額的に多いだろう。また、一件あたりの支払いや受け取りの金額も、預金通貨の方が大きい。こうした状況を考えると、世の中全体を見ても、実は通貨の多くが印刷されておらず、帳簿上の数字として存在していることに気づくだろう。
日本の現金通貨と預金通貨
日本の現金通貨のうち、紙幣は中央銀行である日本銀行(日銀)が発行する“日本銀行券”。硬貨は日本政府の財務省が発行している1円玉から500円玉があり、これらは“貨幣”とも呼ばれる。日本銀行券の発行残高は、2021年11月末で117兆6,523億円に上る。一方、硬貨の流通高は5兆567億円で、日本銀行券の4.3%にすぎない。
これに対して預金通貨は、個人や企業が金融機関に保有している預金である“金融機関預金”に加え、金融機関などが中央銀行に保有している預金である“中央銀行預金”の二種類がある。中央銀行預金は中央銀行が世の中に直接供給している預金通貨を意味する。
日銀が直接供給している預金通貨の規模は、“日本銀行当座預金”(日銀当預)の残高を見れば分かる。日銀当預は日銀が金融機関から受け入れている当座預金。銀行間の決済などは、この日銀当預での口座振替で処理される。
 日銀当預の残高は日本全体に直接供給された預金通貨の規模だ。2021年11月末の日銀当預残高は537兆7,354億円であり、現金通貨の約4.4倍に達する。
日銀当預の残高は日本全体に直接供給された預金通貨の規模だ。2021年11月末の日銀当預残高は537兆7,354億円であり、現金通貨の約4.4倍に達する。
このように手で触ることができる現金通貨よりも、帳簿上の記録である預金通貨の方がはるかに多い。
現金通貨は必要に応じて預金通貨から作られる。例えば、市中銀行が日銀当預からの引き出しを日銀に要求すると、その金額の分だけ口座残高の預金通貨が減少し、現金通貨である日本銀行券が引き渡される。こうした日銀当預からの引き出しというプロセスを通じ、預金通貨から現金通貨が作られる。これを日本銀行券の発行という。
つまり、日本銀行券は日銀が自らの意思で印刷するのではない。「お金をジャンジャン刷れば良い」という言説を唱える人は、こうした仕組みを分かっていないと言えるだろう。なお、現金通貨から預金通貨への変更は、日銀当預への預け入れで達成される。これを日本銀行券の還収(かんしゅう)という。
 日本の紙幣は日銀当預からの引き出しで発行される
日本銀行券の発行と還収は、行楽シーズンや会社の給料日などに前後して活発となる。例えば、大型連休の現金需要に備え、市中銀行は日銀当預から日本銀行券を引き出す。連休が明けると、市中銀行は日本銀行券を日銀当預に預け入れる。こうした日本銀行券の発行と還収で、預金通貨である日銀当預は増減する。
日本の紙幣は日銀当預からの引き出しで発行される
日本銀行券の発行と還収は、行楽シーズンや会社の給料日などに前後して活発となる。例えば、大型連休の現金需要に備え、市中銀行は日銀当預から日本銀行券を引き出す。連休が明けると、市中銀行は日本銀行券を日銀当預に預け入れる。こうした日本銀行券の発行と還収で、預金通貨である日銀当預は増減する。
預金通貨の創造
現金通貨は預金通貨の引き出しで作られる。では、預金通貨はどのように創造されるのだろう。現在の日本では、日銀が何らかの金融資産などを買い取り、その支払いとして日銀当預に金額を書き込むことで、預金通貨が創造される。それゆえ、預金通貨は“万年筆マネー”とも呼ばれる。
日銀が買い取る資産の代表は国債。そのほかにETF(指数連動型上場投資信託受益権)やJ-REIT(不動産投資法人投資口)などが挙げられる。
つまり、日銀がその保有資産として、国債、ETF、J-REITを買えば買うほど、帳簿上の数字である預金通貨が増えることになり、それが紙幣など現金通貨の母体となる。
日銀が買い取った国債、ETF、J-REITは、日銀の貸借対照表(バランスシート)で、資産の部に計上される。一方で支払いに使った日銀当預の残高は、計上先が負債の部となる。日銀当預の引き落としで生まれる日本銀行券も、負債の部に計上される。
日銀当預と銀行券の増加
お金をジャンジャン刷ることはできないが、日銀は資産を買い取ることで、預金通貨を創造できる。では、その預金通貨はどのくらい増えているのだろう?
日銀のバランスシートを見ると、負債の部に計上された日銀当預の残高は、2021年9月末で541兆6,620億円、日本銀行券の発行残高は116兆7,875億円だった。
これらを2015年9月末と比較すると、日銀当預の残高は2.2倍に膨らんでいるが、日本銀行券の発行残高は1.3倍にしかなっていない。“日銀はジャンジャンと預金通貨を創造している”のだが、現金通貨はなかなか増えない。そもそも昔から現金通貨はそれほど必要とされないし、電子マネーが普及している今日ではなおさらだろう。
 「お金をジャンジャン刷れば良い」という言説に応え、前述のように日銀は可能な範囲で通貨の創造に励んでいる。しかし、そうした言説を唱える人は往々にして、こうした数字や仕組みを知らずに、日銀を批判しがちだ。
「お金をジャンジャン刷れば良い」という言説に応え、前述のように日銀は可能な範囲で通貨の創造に励んでいる。しかし、そうした言説を唱える人は往々にして、こうした数字や仕組みを知らずに、日銀を批判しがちだ。
日銀バランスシートの膨張
日銀が買い取った国債、ETF、J-REITは、資産の部に計上されている。2021年9月末の状況を見ると、国債が528兆296億円、ETFが36兆2,051億円、J-REITが2,936億円だった。
これらを2015年9月末と比較すると、長年買い続けている国債が1.7倍にとどまった一方、ETFは5.8倍、J-REITは2.6倍だった。
かつては“日銀券ルール”と呼ばれる日銀の自主規制があった。これは日銀が保有する長期国債の残高を日本銀行券の残高以下に収めるというルール。国の債務である国債を日銀が無制限に引き受けることを抑止するのが目的で、2001年に設定された。
 しかし、2013年4月に“量的・質的金融緩和”が導入されると、日銀券ルールは適用が一時停止された。その結果、2021年9月末で日銀が保有する長期国債は503兆5,029億円に達し、日本銀行券の発行残高の4.3倍に膨らんでいる。
しかし、2013年4月に“量的・質的金融緩和”が導入されると、日銀券ルールは適用が一時停止された。その結果、2021年9月末で日銀が保有する長期国債は503兆5,029億円に達し、日本銀行券の発行残高の4.3倍に膨らんでいる。



この6年間の推移を見ても、日銀は預金通貨を2.2倍に増やした。そのために自主規制を崩し、国債などの金融資産を大規模に買い取っている。その結果、日銀の資産と負債は膨張が続いている。

日銀の総資産は2021年9月末で724兆579億円に達し、2015年9月末に比べて2.0倍となった。2021年9月末の総負債は719兆6,272億円で、同じく2.0倍に膨らんでいる。
その一方で、2021年9月末の純資産は4兆4,308億円で、2015年9月末の1.2倍に過ぎない。総資産に対する総負債の割合は、2015年9月末でも98.97%という超高水準だったが、それが2021年9月末には99.39%に達している。
信用貨幣を支える仕掛けに、“発行者の財務の健全性”があることを先に紹介した。この日銀バランスシートの現状という事実をどう捉えるかについては、さまざまな意見が出ているが、金融の門外漢にも不安を感じさせるには十分な数字ではないだろうか?
日銀当預の構造
市中銀行が日銀当預に預け入れる金額は、“準備預金制度”の準備率に基づき、最低預金額が決まっている。この最低でも日銀当預に預け入れなければならない金額を“法定準備預金額”(所要準備額)という。これを満たせない金融機関には、ペナルティが課されることになる。



 日銀当預の残高は前述のように2021年9月末で約541兆6,620億円だが、うち約480兆6,127円が準備預金だ。
日銀当預の残高は前述のように2021年9月末で約541兆6,620億円だが、うち約480兆6,127円が準備預金だ。
日本では1991年10月まで、この準備率を上下させることで、金融の緩和と引き締めを実施していた。これを“準備率操作”という。しかし、現在では操作目標が“無担保コールレート”(オーバーナイト物)となり、準備率操作は実施されていない。
オーバーナイト物とは、銀行間の貸借取引で、今日借りて翌営業日に返す際に適用される金利を意味する。これは“翌日物金利”とも呼ばれる。短期金融市場が発達した国では、金融政策の操作目標が、オーバーナイト物となっている。一方、中国本土は現在でも準備率操作が重要な金融政策手段の一つであり、その動きは中国経済に大きな影響を及ぼす。
日銀当預の残高のうち、法定準備預金額を超える部分を“超過準備”という。日銀当預の預金は無利息だったが、2008年11月以降は“補完当座預金制度”に基づき、超過準備には利息が付されることになった。
2016年1月に“マイナス金利付き量的・質的金融緩和”が導入されると、日銀当預の残高は三層構造に変化した。従来通り無利息の部分を“マクロ加算残高”という。これに対してプラスの金利が付される部分は“基礎残高”、マイナス金利が適用される部分は“政策金利残高”と呼ばれる。
補完当座預金制度が適用される当座預金の残高は、2021年9月末で約515兆2,747億円。内訳はプラス金利の適用残高が207兆4,502億円、ゼロ金利の適用残高が282兆1,962億円、マイナス金利の適用残高が25兆6,282億円となっている。
日銀当預の増減
市中銀行が日銀からの引き出しや預け入れを行うことで、預金通貨である日銀当預の残高が増減することは、すでに説明した。このほかに日銀当預が増減する要因として、財政資金の受け払いがある。
政府が個人の年金や企業の公共事業費などを支払う場合、日銀が預かる政府預金の残高を減らし、日銀当預の残高を増やす振替決済が実施される。こうして市中銀行に資金が渡り、お金が個人や企業に届く。逆に、政府が個人や企業から税金などを受け入れると、日銀当預の残高が減少し、政府預金の残高が増えることになる。
日銀当預の残高は2021年9月末で541兆6,620億円に上るが、これに対して政府預金は26兆913億円となっている。
政府が実施する“為替介入”(外国為替平衡操作)も、日銀当預が変動する要因だ。“円売りドル買い介入”では、財務省が“国庫短期証券”(TDB)という国債の一種を発行し、日本円の資金を調達。そうして調達した日本円を使い、米ドルを買う。一方、“円買いドル売り介入”では、財務省の“外国為替資金特別会計”(外為特会)の米ドル資金を使い、日本円を買う。

 為替介入は財務省の資金を投入するため、これにともなう日本円の決済は、財政資金の受け払いと同じく、政府預金と日銀当預の振替決済となる。それゆえ、為替介入も日銀当預の増減要因となる。
為替介入は財務省の資金を投入するため、これにともなう日本円の決済は、財政資金の受け払いと同じく、政府預金と日銀当預の振替決済となる。それゆえ、為替介入も日銀当預の増減要因となる。
日銀は海外の中央銀行や国際機関からの“円預金勘定”(海外預かり金)を受け入れている。海外の中央銀行と日本の金融機関の間で日本円の受け払いが発生すると、海外預かり金と日銀当預の間で振替決済される。これも日銀当預の増減につながる。なお、海外預かり金は2021年9月末で27兆7,115億円に上る。
日銀の公開市場操作
これらの要因で日銀当預の残高が変動することに備え、日銀は公開市場操作(オペレーション)を実施する。日銀はオペレーションを通じ、資金を供給したり、吸収したりすることで、日銀当預の残高を調節する。
資金供給のオペレーションは、“買いオペ”と呼ばれる。これは日銀が市中銀行などから日銀が国債などの有価証券を買い入れたり、一定期間だけ借り入れたりし、その代金の支払いとして日銀当預に資金を供給する手法を指す。
一方、資金吸収のオペレーションは、“売りオペ”と呼ばれる。これは日銀が市中銀行などに国債や手形などを売却したり、一定期間だけ貸し付けたりし、その代金の受け取りとして日銀当預から資金を引き出す手法を指す。
日銀は資金供給の買いオペを続けている。例えば、2021年9月は“国債買入オペ”(変動利付債、物価連動債を除く)だけでも15回実施された。これらのオファー額は合計5兆6,500億円で、入札によって買い入れ先が決まる。2021年9月の応札額は合計13兆6,319億円で、落札額は合計5兆6,600億円。これだけの資金が日銀当預に供給された一方で、買い入れた国債が日銀の保有資産に追加された。
2021年9月に実施されたオペレーションには、“国債買入オペ”(変動利付債、物価連動債)、“TDB買入オペ”、“コマーシャルペーパー(CP)等買入オペ”、“社債等買入オペ”、“ETF買入オペ”などがあり、日銀が大量の有価証券を保有資産として取得する代わりに、日銀当預に膨大な資金が供給された。
日本のマネタリーベース
中央銀行や政府が直接供給した現金通貨と預金通貨の総量を“マネタリーベース”という。日本では現金通貨である“日本銀行券の発行残高”と“硬貨の流通残高”に加え、預金通貨である“日銀当預の残高”の合計が、マネタリーベースと定義される。
日本のマネタリーベースは2021年9月末で約663兆4,869億円。その内訳は日銀当預の残高が約541兆6,620億円、日本銀行券の発行残高が約116兆7,875億円、硬貨の流通高が5兆374億円だった。
1996年12月末のマネタリーベースは58兆514億円で、2021年9月末の8.7%に過ぎなかった。その内訳を見ると、日本銀行券の発行残高は50兆6,711億円だったのに対し、日銀当預の残高はわずか相当する3兆4,626億円だった。
 日銀当預の残高が日本銀行券の発行残高を上回ったのは、量的・質的金融緩和が始まった直後の2013年6月末。2021年9月末と1996年12月末を比較すると、日本銀行券の発行残高が2.3倍なのに対し、日銀当預の残高は156.4倍。マネタリーベース全体では11.4倍となった。
日銀当預の残高が日本銀行券の発行残高を上回ったのは、量的・質的金融緩和が始まった直後の2013年6月末。2021年9月末と1996年12月末を比較すると、日本銀行券の発行残高が2.3倍なのに対し、日銀当預の残高は156.4倍。マネタリーベース全体では11.4倍となった。
“ジャンジャンお金を刷れ!”という批判の声もあるが、このように日銀は物凄いペースで通貨の創造を続けている。
信用創造と貨幣乗数
“通貨の供給量”であるマネタリーベースに対し、個人、法人、地方公共団体などの“通貨保有量“は、これをはるかに上回る。
通貨の供給者である中央銀行や政府を除いた個人、法人、地方公共団体などを“通貨保有主体”と呼ぶ。そして、通貨保有主体が保有する通貨の総量を“マネーストック”(マネーサプライ)という。マネーストックは通貨の範囲に応じて、M1、M2、M3などがある。数字が大きいほど、通貨に含める範囲が広い。
日銀や政府が直接供給したマネタリーベースは、前述のように2021年9月末で約663兆4,869億円。これに対して通貨保有主体が保有する現金通貨と預金通貨は、約1.5倍の約977兆円に上る。この金額をマネーストックM1という。
このM1の範囲を広げ、“解約すれば支払いに使える定期性預金などの準通貨”、“通貨のように支払いに使える譲渡性預金(CD)”の二つを加えると、マネーストックM2となる。2021年9月末のマネーストックM2は1,169兆2,000億円で、マネタリーベースの約1.8倍だ。
 通貨の保有量が供給量よりも多いのは、別に外貨を持っているからではない。供給された通貨が、資金の貸し出しを通じて、通貨保有主体の保有残高が増えたのだ。これを“信用創造”という。それは以下のような仕組みだ。
通貨の保有量が供給量よりも多いのは、別に外貨を持っているからではない。供給された通貨が、資金の貸し出しを通じて、通貨保有主体の保有残高が増えたのだ。これを“信用創造”という。それは以下のような仕組みだ。
【融資と預金の繰り返し】
日銀が100億円をA銀行に供給する。
そのうち80億円をA銀行はB社に融資する。
B社は借り入れた80億円をC銀行に預け入れた。
C銀行はB社から受け入れた80億円のうち、60億円をD社に融資した。
D社は借り入れた60億円をE銀行に預け入れた。
E銀行はD社から受け入れた60億円のうち、40億円をF社に融資した。
F社は借り入れた40億円をG銀行に預け入れた。
G銀行はF社から受け入れた40億円のうち、20億円をH社に融資した。
H社は借り入れた20億円をI銀行に預け入れた。
【保有残高】
A銀行の未融資分:20億円
B社がC銀行に保有する預金:80億円
C銀行の未融資分:20億円
D社がE銀行に保有する預金:60億円
E銀行の未融資分:20億円
F社がG銀行に保有する預金:40億円
G銀行の未融資分:20億円
H社がI銀行に保有する預金:20億円

日銀の供給量100億円に対し、A銀行からI銀行までの保有残高は合計280億円となった。うち銀行の未融資分は合計80億円、企業の預金残高は合計200億円となる。
マネタリーベースに対するマネーストックの比を“貨幣乗数”(信用乗数、通貨乗数)という。上記の例では貨幣乗数2.8倍(280%)ということになる。
日本では2013年4月に量的・質的金融緩和が導入され、マネタリーベースが急拡大したが、マネーストックの伸びはそれに追いついていない。このため日本は貨幣乗数の低下が続いている。
2021年9月末のマネーストックM2で考えた場合、日本の貨幣乗数は約1.8倍ということになる。なお、同時点の香港の貨幣乗数は約3.8倍。中国本土では約7.2倍に達する。こうした数字を見ると、日本の金融政策は行き詰まり感がぬぐえない。


日本円と香港ドルの違い


 これまで日本円の概要について解説したのは、香港ドルの特異性を理解するためだ。いよいよ、ここから本題である香港ドルの話に入ろう。香港ドルはさまざまな点で、日本円と異なる通貨だ。
これまで日本円の概要について解説したのは、香港ドルの特異性を理解するためだ。いよいよ、ここから本題である香港ドルの話に入ろう。香港ドルはさまざまな点で、日本円と異なる通貨だ。
香港ドルは日本円のような信用貨幣ではなく、現在も本位貨幣だ。日本円は変動相場制だが、香港ドルは固定相場制。香港ドルには当局が積極的に為替介入しなくても、固定相場が自然と実現する仕組みが備わっている。
発券銀行を比較すると、日本では中央銀行である日本銀行だけだが、香港では香港上海匯豊銀行(HSBC)、渣打銀行(香港)(スタンダード・チャータード銀行)、中国銀行(香港)(中銀香港)という三つの民間銀行に、香港ドル紙幣の発券業務が委ねられている。
香港は金融政策の自主権を放棄している。香港ドルをめぐる金融緩和や金融引き締めを香港の金融当局が自ら決定することはない。日銀当預のようなものは存在するが、香港の通貨当局がその総量を自主的に動かすこともない。
なお、香港域内では香港ドル以外に、米ドルや人民元などの外貨も、広く流通している。なぜなら、外貨の使用と流通を禁じる法律がないからだ。外貨の使用と流通を禁じる法律は1913年に制定されていたものの、1980年代に廃止された。香港の将来に対する不安から、法定通貨のドラライゼーション(米ドル化)という最終手段を確保するためだった。外貨の使用と流通を禁じる法律は、返還後の香港でも制定されていない。
 こうした事情を背景に、香港のマネーストック統計には、香港ドルと外貨の二種類がある。2021年9月末のマネーストックM2は総額16兆656億香港ドルで、内訳は香港ドルが8兆851億香港ドル、外貨が7兆9,805億香港ドル相当となっている。香港ドルと外貨の保有量は拮抗している。
こうした事情を背景に、香港のマネーストック統計には、香港ドルと外貨の二種類がある。2021年9月末のマネーストックM2は総額16兆656億香港ドルで、内訳は香港ドルが8兆851億香港ドル、外貨が7兆9,805億香港ドル相当となっている。香港ドルと外貨の保有量は拮抗している。
このように香港ドルと日本円の相違点は多岐にわたる。そこで、香港ドルの仕組みを詳しくみてみよう。香港の通貨史については、この連載の第二十九回~第三十一回で紹介したが、今回はさらに掘り下げた内容となる。
外貨基金の誕生
英領香港は1935年11月9日に通貨条例(後の外貨基金条例)を制定し、銀本位制からの離脱を決定。通貨条例が同年12月6日に発効すると、香港政庁は外貨基金(外匯基金)を創設し、民間からの銀貨回収を始めた。なお、この外貨基金は英語で“The Exchange Fund”といい、翻訳によっては“為替基金”とも呼ばれる。
銀貨の回収は、正貨の変更が目的だった。香港の発券銀行や一般銀行は、市民から銀貨や銀塊を買い取り、香港ドルで支払った。さらに発券銀行は一般銀行が回収した銀を買い取り、香港ドルを支払った。こうして香港の銀は、発券銀行に集められた。
発券銀行は集めた銀を外貨基金に売却し、“債務証書”(負債証明書)を受け取った。この債務証書が発券銀行の正貨準備資産とされた。なお、債務証書は英語で“Certificate of Indebtedness”という。
 外貨基金は集めた銀をインドのムンバイで改鋳したうえで、ロンドンの貴金属市場で売却し、英ポンドを入手した。そのうえで発券銀行が保有する債務証書は、1英ポンド=16香港ドルの固定相場で、英ポンドと交換可能とした。つまり、発券銀行が正貨準備資産として保有する債務証書は、英ポンドとの引換券のようなものと言える。
外貨基金は集めた銀をインドのムンバイで改鋳したうえで、ロンドンの貴金属市場で売却し、英ポンドを入手した。そのうえで発券銀行が保有する債務証書は、1英ポンド=16香港ドルの固定相場で、英ポンドと交換可能とした。つまり、発券銀行が正貨準備資産として保有する債務証書は、英ポンドとの引換券のようなものと言える。
こうして香港ドルは正貨を銀から英ポンドに変更。香港ドルの価値は、1英ポンド=16香港ドルで裏付けられた。英ポンドを正貨とするこの仕組みを英ポンド本位制という。
こうして外貨基金は香港ドル紙幣の発行を支える重要な役割を担うことになった。なお、この連載の第三十回では、外貨基金の創設に至るまでの経緯が詳しく紹介している。
 1970年代に入ると、外貨基金の役割はさらに重要となった。1976年に香港政庁の硬貨発行資産と一般会計が保有する外貨資産が、外貨基金に移管された。さらに香港政庁の財政備蓄も外貨基金の管理下に置かれた。
1970年代に入ると、外貨基金の役割はさらに重要となった。1976年に香港政庁の硬貨発行資産と一般会計が保有する外貨資産が、外貨基金に移管された。さらに香港政庁の財政備蓄も外貨基金の管理下に置かれた。
香港返還後は土地取引の利益が積み立てられた土地基金が、1998年11月1日に外貨基金に組み入れられた。
シニョリッジ
外貨基金は大きなシニョリッジ(通貨発行益)を得ている。日本では通貨発行益については、誤った説明が広まっている。そうした誤った説明によると、通貨発行益とは政府や中央銀行が発行した紙幣や硬貨から、その製造コストを控除した分の発行益という。
現金通貨の紙幣は中央銀行が勝手に発行するものではない。前述のように、日本では民間銀行から日銀当預から資金を引き出すことによって、日本銀行券が発行される。日銀が創造できるのは、預金通貨である日銀当預の残高だけだ。日本銀行券は日銀当預が形を変えただけに過ぎない。

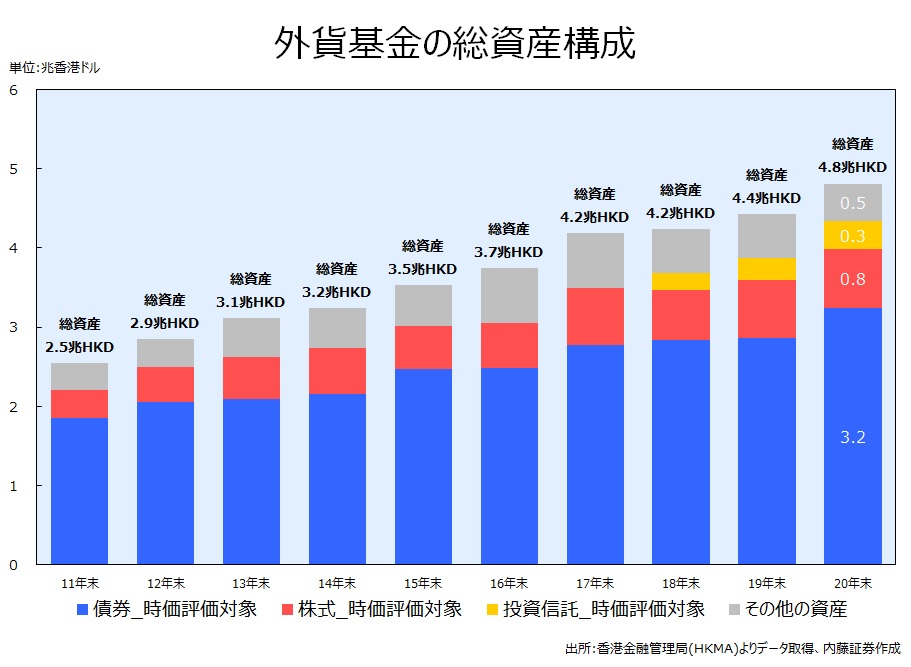 日本銀行券の発行残高と日銀当預の残高は、いずれも日銀バランスシートの負債の部に計上される。誤った説明が正しいというのなら、日本銀行券が負債の部に計上されるのは、おかしな話だ。
日本銀行券の発行残高と日銀当預の残高は、いずれも日銀バランスシートの負債の部に計上される。誤った説明が正しいというのなら、日本銀行券が負債の部に計上されるのは、おかしな話だ。
通貨発行益とは中央銀行が利払い不要の負債である通貨を創造し、それを金融資産などで運用して得られる利益のことだ。例えば日銀の場合、日銀当預の残高という無利子の負債を増やす一方で、利付きの国債を買い取る。その国債は日銀の資産に計上され、そこから利息を得ている。つまり、日銀は“万年筆マネー”で国債を買い、利益を得ているわけであり、これが通貨発行益だ。
香港の通貨発行益は、もっと分かりやすい。発券銀行が紙幣発行のために米ドルを外貨基金に預託する。すると、外貨基金は発券銀行に渡した債務証書を負債の部に計上する一方、受け入れた米ドルで金融資産を購入し、配当、利息、値上がり益を得ている。
つまり、外貨基金は無利子の米ドルを預かり、それを運用しているわけだ。預金者に利息を支払う銀行と違い、外貨基金は利払い不要の米ドルを調達しているわけであり、これをノーリスクの預金で運用したとしても、儲かることになる。
 香港政府は外貨基金で資産運用していることから、その運用損益は民生予算や福祉予算などに影響する。このため、外貨基金の運用成績が悪かったり、運用成績が良いのに民生や福祉の予算が抑制されたりすると、政府関係者は“守銭奴”とメディアに攻撃される。
香港政府は外貨基金で資産運用していることから、その運用損益は民生予算や福祉予算などに影響する。このため、外貨基金の運用成績が悪かったり、運用成績が良いのに民生や福祉の予算が抑制されたりすると、政府関係者は“守銭奴”とメディアに攻撃される。
1970~1980年代に香港ドルの通貨制度は迷走した。英ポンドが変動相場制に移行したことを受け、1972年7月6日に香港ドルは米ドルとのペッグ制に移行。1973年11月25日からは変動相場制となった。
米ドル本位カレンシーボード制の誕生
 鄧小平とサッチャー首相(1982年)
鄧小平とサッチャー首相(1982年)
 ジョセフ・ヤム(任志剛)氏
ジョセフ・ヤム(任志剛)氏
テレビで香港市民に冷静になるよう求める
(1983年)
 米ドル本位カレンシーボード制の発表記者会見
米ドル本位カレンシーボード制の発表記者会見
右端がジョセフ・ヤム(任志剛)氏
 1979年に入ると、香港返還が意識されるようになり、香港ドルの下落が始まった。1982年9月24日に英国のマーガレット・サッチャー首相が北京で鄧小平と会談。1983年7月12日に英中交渉が正式に始まると、香港ドルの下落が加速した。
1979年に入ると、香港返還が意識されるようになり、香港ドルの下落が始まった。1982年9月24日に英国のマーガレット・サッチャー首相が北京で鄧小平と会談。1983年7月12日に英中交渉が正式に始まると、香港ドルの下落が加速した。
1983年9月に入り、英中交渉の難航が伝わると、香港市民の間にパニックが広がった。香港の将来を悲観した人々は、香港ドルを売り、米ドルを購入。香港ドル安が急速に進み、1979年は1米ドル=5香港ドルほどだった相場が、1983年9月23日には1米ドル=9.60香港ドルとなっていた。
香港市民は香港ドル安による購買力の低下と輸入インフレを見越し、生活物資の買い占めに走った。街中のスーパーマーケットでは、白米やトイレットペーパーが商品棚から姿を消した。
香港返還の14年前に、このような通貨危機を香港は経験していた。そこで採用されたのが、1米ドル=7.8香港ドルで相場を固定する米ドル本位カレンシーボード制だった。この通貨制度は1983年10月17日に始まり、今日に至るまで続いている。つまり、香港の現行通貨制度は、通貨危機から誕生した。米ドル本位カレンシーボード制の香港ドルは、そもそも通貨危機に強いのだ。
米ドル本位カレンシーボード制の誕生については、この連載の第三十一回で詳しく紹介している。発券銀行は外貨基金に米ドルを預託すると、債務証書を取得。この債務証書は発券銀行の準備資産となり、これを裏付けに1米ドル=7.8香港ドルの固定レートで、香港ドル紙幣を発行することが可能だ。一方で発券銀行が債務証書を返還すると、発券銀行は預託した米ドルを外貨基金から引き出すことができる。
上記のような香港ドル紙幣の発行と還収は、発券銀行の特権だ。一般の銀行や個人が外貨基金に香港ドル紙幣を差し出しても、米ドルはもらえない。一般の銀行や個人が香港ドルと米ドルを交換するには、外国為替市場で取引したり、銀行で両替したりするしかない。
疑似中央銀行だったHSBC
香港ドル紙幣の発行と還収に関する米ドル本位カレンシーボード制の仕組みを紹介した。ただし、これは“現金通貨”である紙幣の発行に限った話であり、“預金通貨”には当てはまらない。
そもそも、米ドル本位カレンシーボード制が誕生した1983年当時、日銀当預のような香港ドルの“預金通貨”がどうなっているのかは、香港政庁にとってさえ長年の謎だった。
英領香港には中央銀行が存在しなかった。香港の市中銀行は、最大手のHSBCに当座預金口座を開設。銀行間の取引はHSBCが開発した“CHATS”(クリアリングハウス自動振替システム)というシステムで振替決済されていた。つまり、日本の日銀当預のようなものは、民間銀行であるHSBCが掌握しており、その内情は香港政庁でさえも知る手段がなかった。
理論的に考えれば、HSBCは十分な米ドルを保有していれば、香港ドル紙幣の発行を後回しにし、当座預金口座を通じて“預金通貨としての香港ドル”を供給できる。つまり、預金通貨を創造する能力は、香港政庁ではなく、民間銀行であるHSBCが握っていたことになる。
中央銀行機能の強化
HSBCは銀行間の決済機能を有し、さらに紙幣の発行も可能だったことから、“疑似中央銀行”と呼ばれていた。香港政庁はマネタリーベースをコントロールできず、預金通貨を創造する権利もなかった。
 HSBCメイン・ビルディング(匯豊総行大廈)
HSBCメイン・ビルディング(匯豊総行大廈)
香港島セントラル(中環)
民間銀行のHSBCに大きく依存した英領香港の金融環境は世界的に見ても異常であり、中国への主権返還を迎えるのに当たり、大きな障害になることは明らかだった。しかし、香港の振替決済システムはHSBCのCHATSしかなかった。
そこで香港政庁は1988年7月に新制度を導入。外貨基金にHSBCが当座預金口座を設けるというルールを課した。そのうえで、この外貨基金の当座預金口座の残高は、HSBCがCHATSで管理する銀行間の決済残高以上に保つことを義務づけ、さらに罰則金利メカニズムを通じ、香港政庁が香港ドル資金の流動性を間接的に調整できるようにした。
これで香港政庁は1988年7月から、間接的ながらもマネタリーベースの状況を知ることができるようになった。だが、HSBCのCHATSに依存する状況は変わらず、大きな課題として残された。
1990年11月に国際決済銀行(BIS)でG10諸国が、国際的な多通貨・多角的ネッティングシステムついて、6項目の最低基準を定めた。提唱者の名を取って、これを“ランファルシー基準”という。
 アレクサンドル・ランファルシー(左)
アレクサンドル・ランファルシー(左)
“ユーロ創設の父”と呼ばれる人物
(1997年6月)
HSBCのCHATSに依存している香港は、ランファルシー基準のうち、4項目で完全に不適格。残る2項目でさえ、胸を張って適格と言える有様ではなかった。民間銀行のHSBCが銀行間取引の振替決済を担っていることは、“ファイナリティ”(決済完了性)が法的に明確ではないことを意味し、こうした点などが問題だった。
こうした状況を背景に、香港政庁が独自の振替決済システムを構築することは、1997年6月30日の主権返還までに解決すべき目標となった。
EFN発行とCMUシステム
振替決済システムの構築という目標に加え、債券市場の構築と香港ドル資金の流動性調節能力の確保も、大きな課題だった。これを解決するために、香港政庁は1990年3月13日から“外貨基金・短期債券”(EFN)の発行を始めた。
EFNについては「香港の国債のようなもの」という説明も見受けられるが、発行者は外貨基金であり、その発行目的は香港政庁の歳入確保ではない。EFNの発行、貸借、償還などを通じ、香港ドル資金の流動性と金利水準の調節能力を強化することが目的だった。このようにEFNは“香港の国債”ではなく、“香港ドル資金の流動性を調節するためのツール”に過ぎない。
最初のEFNは償還期間が3カ月で、毎週1回3億香港ドルずつ発行された。1990年10月には半年物と1年物のEFNも発行。1993年には償還期間が1年を超える“外貨基金・中期債券”(EFB)の発行も始めた。
EFNやEFBの発行を支えたのは、1990年に稼働した“CMUシステム”(セントラル・マネーマーケット・ユニット)だった。これは債券の発行、清算、決済、寄託をパーパレスで処理するシステム。1993年12月には“その他の香港ドル建て債券”の取引にも使われ、1994年12月には香港域外のシステムに連結し、海外からも香港ドル建て債券の取引が可能になった。
1996年1月には“香港ドル建て以外の債券”にもサービスを拡大。現在では中央政府の人民元建て国債の海外発行などにも、CMUシステムが使われる。CMUシステムは国際金融センターの香港を支える重要な金融インフラとして、今日に至るまで機能している。
なお、香港の国債に相当する債券は、EFNやEFBではなく、政府債券(GB)という。政府債券の発行を認める「借款条例」は、2009年7月8日に立法会で承認された。未償還残高は1,000億香港ドル以内という条件付きで、2009年7月10日に発効。この条件は2021年7月21日に3,000億香港ドルに引き上げられた。
 通脹掛鈎債券(iボンド)の広告
GBの種類は多様だ。機関投資家向けの機構債券(インスティチューショナル・ボンド)や個人向けの零售債券(リテール・ボンド)のほか、65歳以上の香港市民向けの銀色債券(シルバー・ボンド)、低炭素経済(ローカーボン・エコノミー)の推進に向けた緑色債券(グリーン・ボンド)、イスラム圏向けの伊斯蘭債券(スクーク)、物価に連動する通脹掛鈎債券(iボンド)などが発行されている。
通脹掛鈎債券(iボンド)の広告
GBの種類は多様だ。機関投資家向けの機構債券(インスティチューショナル・ボンド)や個人向けの零售債券(リテール・ボンド)のほか、65歳以上の香港市民向けの銀色債券(シルバー・ボンド)、低炭素経済(ローカーボン・エコノミー)の推進に向けた緑色債券(グリーン・ボンド)、イスラム圏向けの伊斯蘭債券(スクーク)、物価に連動する通脹掛鈎債券(iボンド)などが発行されている。
最後の貸し手
EFNやEFBの流通量が増えたことを受け、1992年6月に“流動性調節ファシリティ”(LAF)が稼働した。この流動性調節ファシリティは、中央銀行の役割の一つである“最後の貸し手”としての機能を果たす。
市中銀行はEFNやEFBなどを担保として差し入れ、外貨基金の流動性調節ファシリティから香港ドル資金を借り入れることが可能となった。それと同時に、市中銀行は流動性調節ファシリティを通じ、過剰な香港ドル資金を一定の金利で外貨基金に預け入れることもできた。
こうして香港政庁は香港ドル資金の流動性調節能力を強化した。なお、流動性調節ファシリティは1998年9月に廃止され、現在は“ディスカウント・ウィンドウ”という仕組みが、似たような役割を担っている。
香港金融管理局の誕生
 香港島の国際金融中心
香港島の国際金融中心
香港金融管理局が入居する
高さ412メートル、94階建て
1993年4月1日に銀行業の監督機関である銀行業監理処が、米ドル本位カレンシーボード制を支える外匯基金管理局と合併し、香港金融管理局(HKMA)が発足した。
香港金融管理局は中央銀行としての役割を担い、香港政庁からの独立性を有した機構。金融政策のほか、銀行、通貨、外貨基金の管理を担い、財政長官(財政司司長)に対して責任を負う。初代総裁に就任したのは、外貨基金管理局の任志剛(ジョセフ・ヤム)局長だった。
香港金融管理局は1995年に“即時グロス決済”(RTGS)システムの構築に着手した。RTGSとは振替決済の指図が持ち込まれしだい、一つ一つ即実行するシステムだ。
口座振替の手法には、“時点ネット決済”(DTNS)という方法もあり、これは一定時点まで振替指図を蓄え、受払差額を決済するというもの。RTGSはDTNSに比べ、決済が即座に完了することから、システミック・リスクを大幅に抑えることができる。RTGSは1980年代から世界各国の中央銀行で採用が始まり、やがて国際標準となった。
香港金融管理局のRTGSシステムは1996年12月に完成。これは米国、スイス、英国に次いで、世界で4番目のRTGSシステムだった。債券取引のCMUシステムは、このRTGSシステムと連結し、証券の受け渡しと資金の決済を同時に実行する“DvP決済”のサービスを提供するようになった。
銀行がHSBCに開設していた当座預金口座は、すべてRTGSシステムで処理する外貨基金の当座預金口座に移された。こうして香港金融管理局は外貨基金を通じ、マネタリーベースのカギを握る当座預金残高を全面的に管理できるようになり、HSBCのCHATSに依存していた状況は完全に解消された。
外貨基金に開設された銀行間決済用の当座預金口座の残高は、“アグリゲート・バランス”(総結余)と呼ばれ、これは日本の日銀当預に相当する。
香港ドルのマネタリーベース
こうして香港金融管理局が管理する外貨基金は、香港ドルのマネタリーベースの管理権を掌握し、日本の日銀のような通貨当局となった。外貨基金のバランシートには、日銀と同じく負債の部にマネタリーベースの各項目が計上されている。
 1935年の債務証書
発券銀行が紙幣の準備資産として保有する債務証書は、日銀のバランスシートで言えば、発行銀行券に相当するもので、これは現金通貨に分類される。香港政府が発行した10香港ドル紙幣と硬貨も現金通貨だ。一方、日銀当預の残高に相当するアグリゲート・バランスは預金通貨。これらはいずれも外貨基金の負債として計上され、香港のマネタリーベースの一部とされる。
1935年の債務証書
発券銀行が紙幣の準備資産として保有する債務証書は、日銀のバランスシートで言えば、発行銀行券に相当するもので、これは現金通貨に分類される。香港政府が発行した10香港ドル紙幣と硬貨も現金通貨だ。一方、日銀当預の残高に相当するアグリゲート・バランスは預金通貨。これらはいずれも外貨基金の負債として計上され、香港のマネタリーベースの一部とされる。
日本と香港のマネタリーベースは、上記の部分では共通している。しかし、香港にしかない特徴もある。それは、EFNやEFBの未償還残高が、香港のマネタリーベースに含まれるという点だ。この点を見ても、EFNやEFBが“香港の国債”ではないことが分かる。
外貨基金がEFNやEFBを発行すると、預金通貨であるアグリゲート・バランスの香港ドル資金が減少し、EFNやEFBの未償還残高が増加する。そして、償還期限を迎えると、EFNやEFBの未償還残高が減少し、アグリゲート・バランスの香港ドル資金が増加する。
こう考えれば、なぜEFNやEFBの未償還残高が、マネタリーベースの一部に含まれるのかが分かるだろう。EFNやEFBは香港ドル資金が一時的に姿を変えているのに過ぎないからだ。
アグリゲート・バランスとEFNやEFBの未償還残高は、いずれも外貨基金の負債に計上される。つまり、EFNやEFBの発行や償還が起きても、外貨基金の負債の部は利息分程度しか変動しない。それゆえ、EFNやEFBの発行や償還は、マネタリーベースの各項目間の移転に過ぎないとされる。
 2021年9月末の香港のマネタリーベースは約2兆1,187億香港ドルで、内訳は日本の発行銀行券に相当する債務証書が5,789億香港ドル、香港政府が発行した10香港ドル紙幣と硬貨が132億香港ドル、日銀当預の残高に相当するアグリゲート・バランスが4,375億香港ドル、EFNとEFBの未償還残高が1兆891億香港ドルに上る。
2021年9月末の香港のマネタリーベースは約2兆1,187億香港ドルで、内訳は日本の発行銀行券に相当する債務証書が5,789億香港ドル、香港政府が発行した10香港ドル紙幣と硬貨が132億香港ドル、日銀当預の残高に相当するアグリゲート・バランスが4,375億香港ドル、EFNとEFBの未償還残高が1兆891億香港ドルに上る。
香港ドルの創造
香港ドルのマネタリーベースを構成する4項目のうち、敏感に変動するのがアグリゲート・バランスだ。紙幣や硬貨は発行したり、還収したりする動きが緩慢であり、あまり変動しない。また、EFNやEFBには償還期間があり、期限を迎えるまでは、香港ドル資金に戻ることがなく、変動は緩やかだ。
これに対してアグリゲート・バランスは、香港ドルの預金通貨であり、時に大きく増減する。それは香港ドル預金通貨の創造と消滅のメカニズムに深くかかわっている。
日銀は国債、ETF、J-REITなどの金融資産を買い入れ、その支払金額を日銀当預に書き込むことで、日本円の預金通貨を創造する。一方、香港ドルの発行は米ドルを中心とした外貨で100%裏付けることが法律で決まっている。
つまり、外貨基金が外貨資産を増やすと、香港ドル資金の総量も増加する。逆に、外貨基金が外貨資産を減らすと、香港ドル資金の総量は減少する。
外貨基金が保有する外貨資金の増減は、香港ドルと外貨の交換、すなわち外国為替取引で生じる。外貨基金が香港ドルで外貨を買い入れると、預金通貨が創造される。外貨基金が買い入れた外貨は、保有資産としてバランスシートの資産の部に計上。その外貨購入の支払いは、アグリゲート・バランスに香港ドルの金額を書き込むことで完了する。こうして香港ドルの預金通貨が増加し、アグリゲート・バランスとマネタリーベースも拡大する。
一方、外貨基金が外貨で香港ドルを買い入れると、預金通貨が消滅することになる。外貨基金は保有資産の外貨を取り崩し、支払いに充てる。香港ドルの受け取りは、その金額分をアグリゲート・バランスから消去することで完了する。こうして香港ドルの預金通貨が減少し、アグリゲート・バランスとマネタリーベースも縮小する。
香港ドル相場の金利裁定メカニズム
日本の日銀当預に相当するアグリゲート・バランスが変動するということは、流動的な香港ドル資金の総量が増減することを意味する。アグリゲート・バランスが増えるということは、香港ドル余剰資金が増加するということであり、資金貸借のコストである金利は低下する。
逆に、アグリゲート・バランスが減るということは、香港ドル余剰資金が減少するということであり、資金貸借のコストである金利は上昇する。このアグリゲート・バランスに連動して香港ドル金利が変動する仕組みは、為替相場の安定につながる。
香港ドルの対米ドル相場は、1米ドル=7.8香港ドルの近辺で安定する。なぜなら、香港ドルは発行時点で、1米ドル=7.8香港ドルの固定レートで価値が裏付けられているからだ。しかし、外国為替市場では香港ドル需要の変化に従い、1米ドル=7.8香港ドル以外の相場で取引が成立する。
例えば、香港ドル需要が強まり、米ドル需要が弱まると、外国為替市場の投資家は1米ドル=7.78香港ドルなどのレートでも、米ドルを売って、香港ドルを買おうとする。一方、香港ドル需要が弱まり、米ドル需要が強まると、投資家は1米ドル=7.82香港ドルなどのレートでも、香港ドルを売って、米ドルを買おうとする。
このように香港ドルは発行時のレートが法律で完全に固定されていても、外国為替市場での取引レートは変動する。しかし、アグリゲート・バランスの増減で生じる香港ドル金利の変化が、外国為替市場の取引レートを安定に向かわせる。
香港ドルは売られ過ぎると、米ドルに対して下落する。そこで、香港ドルの売りを外貨基金が受けると、外貨を支払い、その金額の分だけアグリゲート・バランスの金額を消去する。アグリゲート・バランスが減少すると、余剰な香港ドルは希少になるので、貸し手が少なくなり、金利が上昇する。香港ドルの金利が上昇すると、利息収入を目当てに、香港ドルが買われる。香港ドルが買われると、米ドルに対して上昇に転じる。こうして最終的に香港ドル相場は安定する。
一方、香港ドルが買われ過ぎると、米ドルに対して上昇する。そこで、香港ドルの買いを外貨基金が受けると、外貨を受け取り、その金額の分だけアグリゲート・バランスの金額を追加する。アグリゲート・バランスが増加すると、余剰な香港ドルは潤沢になるので、貸し手が多くなり、金利が低下する。香港ドルの金利が低下すると、利息収入が期待できず、香港ドルが売られる。香港ドルが売られると、米ドルに対して下落に転じる。こうして最終的に香港ドル相場は安定する。
このように香港ドルは、外貨基金が投資家の売買に応じるだけで金利の変動を起こし、容易に対米ドル相場を安定させることができる。これは他の通貨にはない固定相場のメカニズムだが、国際的にあまり知られていない。ヘッジファンドも熟知していなかったようだ。

固定相場の代償
金利裁定メカニズムで為替相場を安定させる香港ドルの仕組みを維持するため、香港は金融政策の自主権を放棄している。この仕組みを維持するには、香港ドルと米ドルの金利水準が、原則的に一致しなければならない。香港ドルと米ドルの金利水準が異なると、一方の通貨に売りや買いが集中し、為替相場の維持が困難になるからだ。
そこで、米国が政策金利を調整すると、それに一致するように香港では公定歩合に相当する香港ドルの金利を機械的に連動させる。つまり、香港ドルの金利水準は、米国の政策金利で決まり、香港政府が操作することはできない。
香港は金融政策の自主権を放棄しているため、バブルや恐慌が起きるリスクが高い。香港の実体経済が過熱気味だったとしても、米国が利下げをすれば、香港ドルの金利水準も低下し、火に油を注ぐことになる。
逆に、香港の実体経済が低迷しても、米国が利上げをすれば、香港ドルの金利水準も上昇し、景気が一段と冷え込むことになる。
そうしたデメリットはあるものの、香港は実体経済に比べ、金融経済や国際貿易の規模がはるかに大きい。2020年の香港の名目域内総生産(GDP)は約2兆6,885億香港ドルだったのに対し、商品貿易額はその3.2倍に相当する8兆5,320億香港ドル、証券市場の売買代金は11.9倍の32兆1,101億香港ドル、時価総額は17.7倍の47兆5,230億香港ドルに達する。
 香港にとって国際金融センターと国際自由貿易港であることの方が、メリットが大きい。そのためには、外国為替相場の固定と資本の自由な移動を確保することが重要であり、その代償として金融政策の自主権を放棄しているわけだ。
香港にとって国際金融センターと国際自由貿易港であることの方が、メリットが大きい。そのためには、外国為替相場の固定と資本の自由な移動を確保することが重要であり、その代償として金融政策の自主権を放棄しているわけだ。
“国際金融のトリレンマ”という言葉がある。それは“自由な資本移動”、“固定相場制”、“独立した金融政策”という自国に有利な三つの政策は、同時に実現することができないという意味。この三つのうち香港は“独立した金融政策”を放棄し、残りの二つを実現している。

1997年のアジア通貨危機で通貨が暴落した国々は、国際金融のトリレンマを無視していた。それが最終的に固定相場制の維持を破綻させることにつながった。一方、香港は“独立した金融政策”を放棄していた。また、中国本土は“自由な資本移動”を制限していた。
アジア通貨危機で香港と中国本土は通貨防衛に成功するが、その理由の一つとして国際金融のトリレンマを無視していなかったことが挙げられる。
アジア通貨危機と香港
この連載の第五十九回で紹介したように、タイ王国のバーツ、フィリピンのペソ、マレーシアのリンギット、インドネシアのルピアが、1997年7月に急落。アジア通貨危機が本格化した。東南アジア諸国の通貨ほどではないが、東アジア諸国の通貨も弱含み始めた。
ある地域の1カ国・地域で通貨が急速に下落すると、そこの輸出競争力は通貨安のおかげで強まる一方で、その周辺の国・地域の製品は割高となり、相対的に不利な状況に陥る。そこで、周辺地域も輸出競争力を保つため、通貨の切り下げに動くことが想定される。通貨危機の連鎖を食い止めるのは、どこかが通貨防衛に成功する必要がある。
通貨の切り下げは、その国・地域に直接投資している外国人投資家にとって最悪の話だ。投資先の通貨が下落することで、自国通貨建てに直すと、海外保有資産が目減りすることになるからだ。対中投資が盛んだった1997年当時、先進国の実業家は人民元や香港ドルの切り下げをかなり心配していた。
中国本土は前述のように“自由な資本移動”を制限していたため、ヘッジファンドも人民元には手の出しようがない。中国本土の周辺地域の通貨安を受け、人民元を切り下げるか否かは、中国政府の政治的判断にかかっていた。中国の金融政策の担当者だった当時の朱鎔基・副首相は、人民元の切り下げを再三にわたって否定し、実際にその通りに行動した。
一方の香港は“自由な資本移動”が可能であり、ヘッジファンドは香港ドルへの攻撃が可能だった。この連載の第五十九回で紹介したように、当時の香港経済は明らかに過熱しており、ヘッジファンドの攻撃対象となる条件が揃っていた。
香港ドルへの攻撃
香港ドルの直物為替相場(スポットレート)は、返還前の半年にわたり1米ドル=7.75香港ドルから少し香港ドル高の水準で推移していた。直物相場とは売買契約から2営業日以内に受け渡しを実行する取引に適用するレートを意味し、現物為替相場ともいう。
しかし、決められた将来の取引価格を決める先物為替相場(フォワードレート)では、すでに異変が起きていた。返還1カ月前の6月3日には恒生銀行(ハンセン銀行)の1年物先物相場は、1米ドル=8香港ドルを超える香港ドル安となっていた。これは1年後にそうした相場になるという予想が広がっていたことを意味する。
香港返還直後の7月3日は直物相場が1米ドル=7.74355香港ドル、1年物先物相場が1米ドル=7.97855香港ドルだった。7月11日にフィリピンがペソの変動幅制限を拡大すると、香港ドルにも下落圧力が加わり、直物相場が1米ドル=7.74735香港ドル、1年物先物相場が1米ドル=8.05235香港ドルとなった。
 1年物先物相場はその後も下落が進み、8月15日には9香港ドルの大台を突破し、1米ドル=9.19950に達した。こうしたなか、台湾の中華民国中央銀行は、10月17日に新台湾ドル相場を市場に任せると突然表明。これを受け、ヘッジファンドの矛先は、中国に返還されたばかりの香港に向いた。
1年物先物相場はその後も下落が進み、8月15日には9香港ドルの大台を突破し、1米ドル=9.19950に達した。こうしたなか、台湾の中華民国中央銀行は、10月17日に新台湾ドル相場を市場に任せると突然表明。これを受け、ヘッジファンドの矛先は、中国に返還されたばかりの香港に向いた。
台湾が新台湾ドルの防衛を放棄した翌営業日の10月20日は、香港ドルの1年物先物相場が1米ドル=9.14200香港ドルに急落。10月21日には1米ドル=9.99750香港ドルとなった。そして、10月22日には2ケタに達し、1米ドル=11.49750香港ドルを記録した。直物相場は引き続き1米ドル=7.74香港ドル台だったが、多くの投資家が香港ドルの急落を予想していた。
1997年10月23日の異変
ヘッジファンドは市中銀行などから香港ドルを借り入れ、それを外国為替市場で売却していた。香港ドルの固定相場が崩れ、急落した後に買い戻し、それを返済すれば、大きな利益を得ることになる。香港ドルを借り入れた際のレートと買い戻した際のレートの差が、ヘッジファンドの利益だ。
市中銀行は外貨基金の流動性調節ファシリティにEFNやEFBなどを担保として差し入れ、香港ドル資金を借り入れていた。流動性調節ファシリティは“最後の貸し手”の役割を果たすべきものだが、それを市中銀行は便利な香港ドル資金の調達先として利用していた。
10月23日は直物相場でも1米ドル=7.5香港ドルの警戒線を突破し、1米ドル=7.69000香港ドルに達した。1年物先物相場に至っては1米ドル=13.69000香港ドルに達した。
 ヘッジファンドは大々的に香港ドルを売り、米ドルを買いあさった。その相手のなったのは香港の外貨基金だ。外貨基金は保有資産の米ドルを使い、香港ドルを買い受けた。外貨基金は保有する米ドルを急速に減らす一方で、購入した分だけ香港ドルの金額をアグリゲート・バランスから消去していった。
ヘッジファンドは大々的に香港ドルを売り、米ドルを買いあさった。その相手のなったのは香港の外貨基金だ。外貨基金は保有資産の米ドルを使い、香港ドルを買い受けた。外貨基金は保有する米ドルを急速に減らす一方で、購入した分だけ香港ドルの金額をアグリゲート・バランスから消去していった。
こうして日本の日銀当預に相当するアグリゲート・バランスから、急速に香港ドル資金が減少した。その当時のアグリゲート・バランスは20億~30億香港ドルが一般的だったが、それが一時はマイナスを記録するほど、香港ドル資金が枯渇。その結果は目に見えていた。
10月23日に香港金融管理局は市中銀行に警告を発した。市中銀行がヘッジファンドに香港ドル資金を貸し付けるために、流動性調節ファシリティを何度も使っていることを批判。そのような市中銀行には、流動性調節ファシリティの利用時に懲罰的金利を適用すると強調した。
アグリゲート・バランスの香港ドル資金は枯渇しているうえ、流動性調節ファシリティから融通することもできない。この状況に市中銀行は狼狽し、何とかして香港ドル資金を確保しようと、高い借入金利を提示した。だが、どんなに高い金利を提示しても、それに応じる銀行は現れなかった。なぜなら、香港ドル資金はほぼ枯渇し、どこの銀行も貸し出せる余裕資金がなかったからだ。
その結果、10月23日の香港銀行間市場では、翌日物金利が年率で300%近くに達した。スタンダード・チャータード銀行の記録によると、この日の銀行間金利の終値は、翌日物が年率100%、1週間物が年率175%、1カ月物が年率30%、3カ月物が年率25%だったほか、6カ月物、9カ月物、1年物はいずれも年率20%だった。

この異常な金利上昇を受け、外国為替市場では香港ドルの買い戻しが進み、10月27日には直物相場が1米ドル=7.73050香港ドルまで回復した。米ドル本位カレンシーボード制に特有のアグリゲート・バランスと金利の変動により、香港ドル相場はヘッジファンドによる最初の本格的な攻撃を撃退した。
勝利の代償
ただ、無傷というわけにはいかなかった。香港株式市場では急激な香港ドル売りと金利上昇を嫌気し、株価が急落。台湾が通貨防衛を放棄した翌営業日の10月20日は、ハンセン指数が大幅安となり、前日比4.6%安で終了した。
その翌日21日にモルガン・スタンレーのストラテジストは、グローバル運用に占めるアジア発展市場の比率を従来の2%から0%に引き下げると発言。香港の株式市場を中心に下落が始まることを示唆した。この発言の影響で、21日のハンセン指数は4.4%安で終了。22日も6.2%安となり、金利が異常に急上昇した23日には10.4%安を記録した。
その後は香港ドルの買い戻しや金利上昇の鈍化を受け、24日にハンセン指数は5日ぶりに急反発し、6.9%高で終了。しかし、27日は5.8%安の急反落。28日には13.7%安の大暴落となり、終値がついに1万ポイントの大台を割り込んだ。29日には3日ぶりに急反発し、18.8%高を記録したが、株式市場は不安定な動きが続いた。

東南アジアの通貨安は、香港最大の証券会社だったペレグリン(百富勤)を経営破綻に追い込んだ。この会社は1988年に作業したばかりだが、香港財界の有力者たちから支援を受け、数年間で急成長。中国本土に積極的に進出し、中国政府系企業の香港上場で何度も主幹事を務めたほか、東南アジアや東アジアにも事業を拡げた。
 ペレグリンを創業した梁伯韜(フランシス・リョン)(左)
ペレグリンを創業した梁伯韜(フランシス・リョン)(左)
本土企業の香港上場を推進し、“レッドチップの父”と呼ばれた
右は共同創業者のフィリップ・トーズ(杜輝廉)
 香港のヤオハン(八佰伴)
ペレグリンは自己資本の4分の1に相当する2億6,500万米ドルをインドネシアのタクシー会社に無担保で融資しており、その焦げ付きが経営破綻のきっかけとなった。1998年1月13日にペレグリンは清算手続きを開始。最終的にペレグリンの中国株部門はフランスのBNPパリバに買収され、“BNPパリバ・ペレグリン”となった。
香港のヤオハン(八佰伴)
ペレグリンは自己資本の4分の1に相当する2億6,500万米ドルをインドネシアのタクシー会社に無担保で融資しており、その焦げ付きが経営破綻のきっかけとなった。1998年1月13日にペレグリンは清算手続きを開始。最終的にペレグリンの中国株部門はフランスのBNPパリバに買収され、“BNPパリバ・ペレグリン”となった。
ペレグリンの経営が破綻すると、香港では正達証券、福権証券、集豊証券などが連鎖倒産した。正達証券は顧客からの預かり資産である株式を勝手に担保として差し出し、銀行から巨額の資金を借り入れていた。福権証券では経営者が顧客の株券と資金を持ち逃げし、行方をくらました。集豊証券では顧客の資産を無断流用していた経営者が香港警察に自首した。
香港の日系企業も経営破綻に追い込まれた。百貨店のヤオハン、大丸、松坂屋は、1997~1998年に相次いで香港から姿を消した。
終わらぬ戦い
ヘッジファンドの攻撃を退けた1997年10月23日、香港政府の曽蔭権(ドナルド・ツァン)財政長官、財経事務及庫務局(FSTB)の許仕仁(ラファエル・ホイ)局長、香港金融管理局の任志剛・総裁はそろって記者会見を開催。香港ドル防衛の決意と自信を表明した。
 曽蔭権・財政長官(中央)
曽蔭権・財政長官(中央)
右は香港金融管理局(HKMA)の任志剛・総裁
左は財経事務及庫務局(FSTB)の許仕仁・局長
アジア通貨危機に立ち向かった三人は、
“財金三剣客”(財政金融の三銃士)と呼ばれた
だが、ヘッジファンドの攻撃はこれで終わらなかった。香港ドルの直物相場レートは死守したが、1年物先物相場は依然として1米ドル=10香港ドル以上の水準にあり、予断を許さぬ状況だった。
香港政府とヘッジファンドの熾烈な戦いは、1998年に本格化する。1997年10月の異変は、攻撃の第一波に過ぎなかった。


 千原 靖弘
千原 靖弘


